灯台のコウモリ_1
- μ
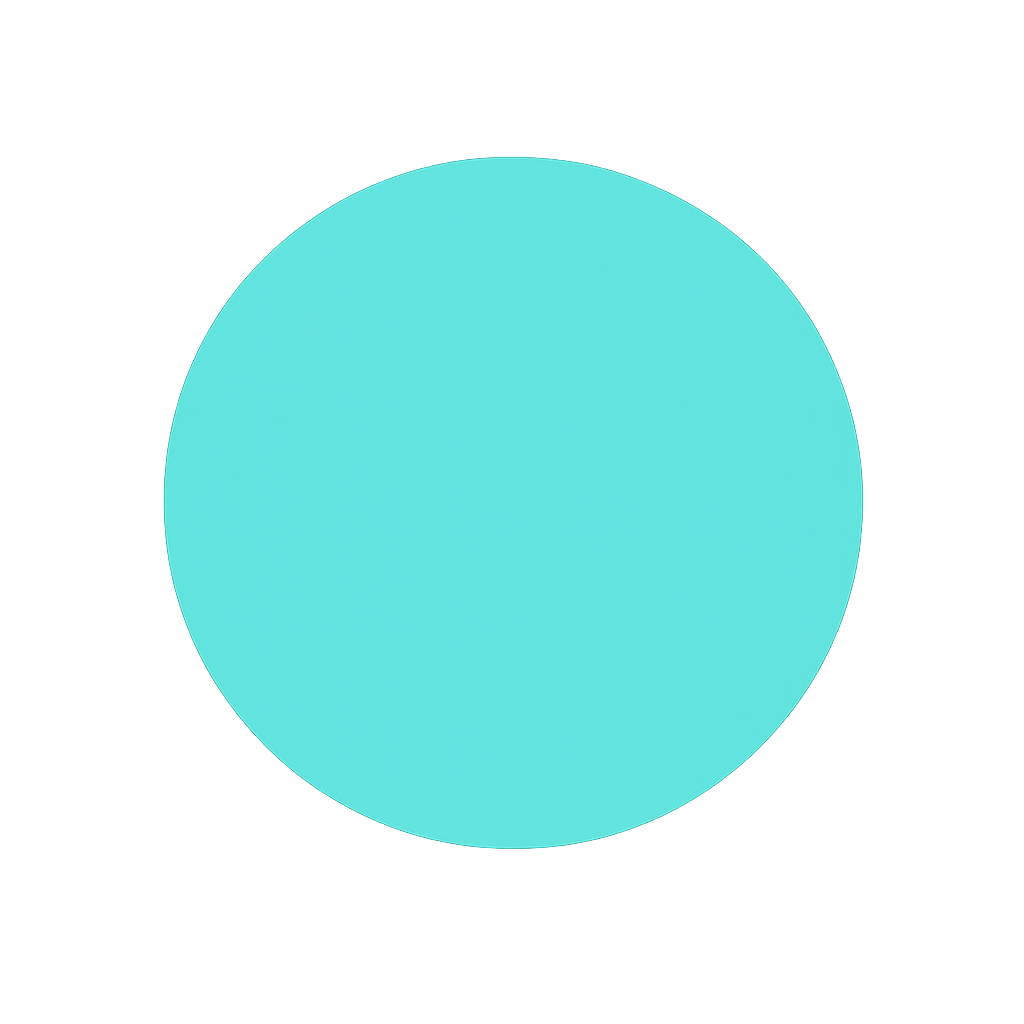
- 8月21日
- 読了時間: 4分
更新日:10月9日
「やあ。コウモリ」
空耳か?と思い見ると、扉は開き影が床にくっきりと人の形を描いていた。
来訪者とは珍しい。
僕は視線を本へと戻し、読み終えていないページを捲る。
「人違いだ。僕はコウモリじゃない」
「じゃあ、なんて呼べばいい?」
面倒臭い。なんだこいつ。
バサ、と本を勢いよく閉じ、天井に視線を送って僕は聞いた。
「僕ら、知り合いか?」
「いいや。初対面」
視線を黴びだらけの天井から影の落ちる床へ。風変わりな来訪者の全身を頭の先から靴の先まで無言で眺める。逆光だが、無表情なのはわかった。
「君は誰だ?」
「界塚伊奈帆」
「年は?」
「八」
「へえ」
想像通りというか、見たままの年齢だ。
見たままの年齢、という言い回しの皮肉さに鼻からふっと息が漏れる。
「君は?」
「は?」
いつの間にか、八歳の子どもがすぐそばに来て僕の顔をじっと見ていた。視線の高さは、椅子に座っている僕と同じくらい。背筋を伸ばした直立は、少年の服装とあまり似つかわしくなく思う。
「君は誰?」
重ねての問い。こちらを見つめる瞳は、遠い記憶の朝焼けめいた暖色だ。少年の靴先を一瞥し、僕はゆっくり脚を組む。
「コウモリだろ。灯台のコウモリ」
それが僕の名前だ。ここに来る人間にとっての。
子どもは朝焼けの瞳を大きく瞬く。
「さっき自分で、コウモリじゃないって言った」
「チッ」
面倒くさいな。こいつの相手。そもそも、変なやつなんだ。廃墟となった岬の灯台へ、遭難でもなくやってきて、僕と会話を試みる。
立ち上がる。高い位置から見下ろすと、栗色の頭髪、つむじの形がはっきり見えた。
「君は僕のなんだ?友だちか?」
「なる?友だち」
「へ?」
「僕は伊奈帆。君の名前は?」
会話のテンポと振り幅についていけない。変な子どもだ。いや、子どもってこんなものか、と思考が記憶の糸を辿る。
真夏の雲が香った気がした。
「ふふっ」
「あ、コウモリが笑った」
「コウモリじゃない」
僕はすう、と息を吸う。久しぶりだ。空気が肺を満たす感じ。たとえ湿った黴臭い地下の空気だとしても、悪くない感覚だ。
生きてるような気分になった。
僕は、八年生きた少年に向けて右手を差し出す。八年だ。瞬くような刹那の生のその途中。この人間は、自分の意思で会いにきた。
岬の亡霊。ーー灯台のコウモリに。
「スレインだ。伊奈帆」
「よろしく、スレイン 」
二つの右手が握手の形で重なった。僕は眉を顰める。ゴツゴツとした硬い感触。
引き戻した手を開くと、穴だらけの歪な小石があった。
「なんだ、これ?」
「なんだと思う?」
問いに問いで返すのは、モテない男の特徴だぞ、と言いたくなったがやめにした。十年経ったら言ってやろう。
僕は、無数の穴に穿たれた石を手のひらで転がす。
この石は、僕の知らない場所にあった。最初は、もっと大きい岩。割れて砕けて、穴が空いた。八歳の少年の手で拾われて、廃墟の地下の、時を忘れたヴァンパイアへと手渡されたこの石は、ぴったりと僕の手の中に収まった。止まった臓器が脈打つような錯覚に襲われる。
「ーー地球の心臓か?」
僕が言うと、伊奈帆はこれ以上なく大きな目を見開いた。虹彩に星が見える。
「ふふっ、あははっ」
伊奈帆は声をあげて笑い出し、しばらくそれは続いた。笑いが収まると、目じりの涙を拭って彼は言った。
「面白いね、コウモリ。いや、スレイン」
「君の笑い方の方が面白い。生まれて初めて笑った?」
「あんな大笑いは、生まれて初めてしたかもね」
じゃあ、スレイン 、と彼は軽やかに踵を返す。
「お土産持って、また来るよ」
僕は少し考えてからこう言った。
「待て、街まで送る」
「君は閉じ込められているんじゃないの?」
街への道を歩く途中、波音を遠くに伊奈帆が聞いた。
「誰がそんなこと……。他に行き場がないだけさ」
伊奈帆が僕を見上げた。星明かりを照り返す彼の顔は、歳より大人びて見える。
「街に入れないんじゃないの?」
「灯りが見えるところまでさ」
灯台を背に、街を前に、どちらも視界に見えない道をただ歩く。星と波の囁きの中。
マリンスノーの海の底を歩くような夜だと思った。
「カイヅカイナホ。君は、この土地の子どもじゃないだろう」
「子ども扱い?」
「子どもだろう」
「今はね」
くす、と笑みが漏れる。その通りだ。伊奈帆は、すぐに大人になるだろう。大人になって、そしてまた、僕を残していなくなる。
首を振る。また、ってなんだ。彼は僕の何でもない。
「さっき、また来る、と言っていたが」
見下ろすと目が合った。八歳にしても幼い面立ちは、遠い国を故郷としている証であり、彼の衣服は風変わりだった。靴先がやけにくたびれて、風の通るゴワゴワとした布地の服だ。
「伊奈帆、君はどこから来て、どこへ行くんだ?」
伊奈帆は波の音に視線を送った。
「海だよ」
「海?」
再び僕の顔を見上げ、伊奈帆は口の端を引き上げる。
「海賊だからさ」



コメント