Blue Bird,_2
- μ
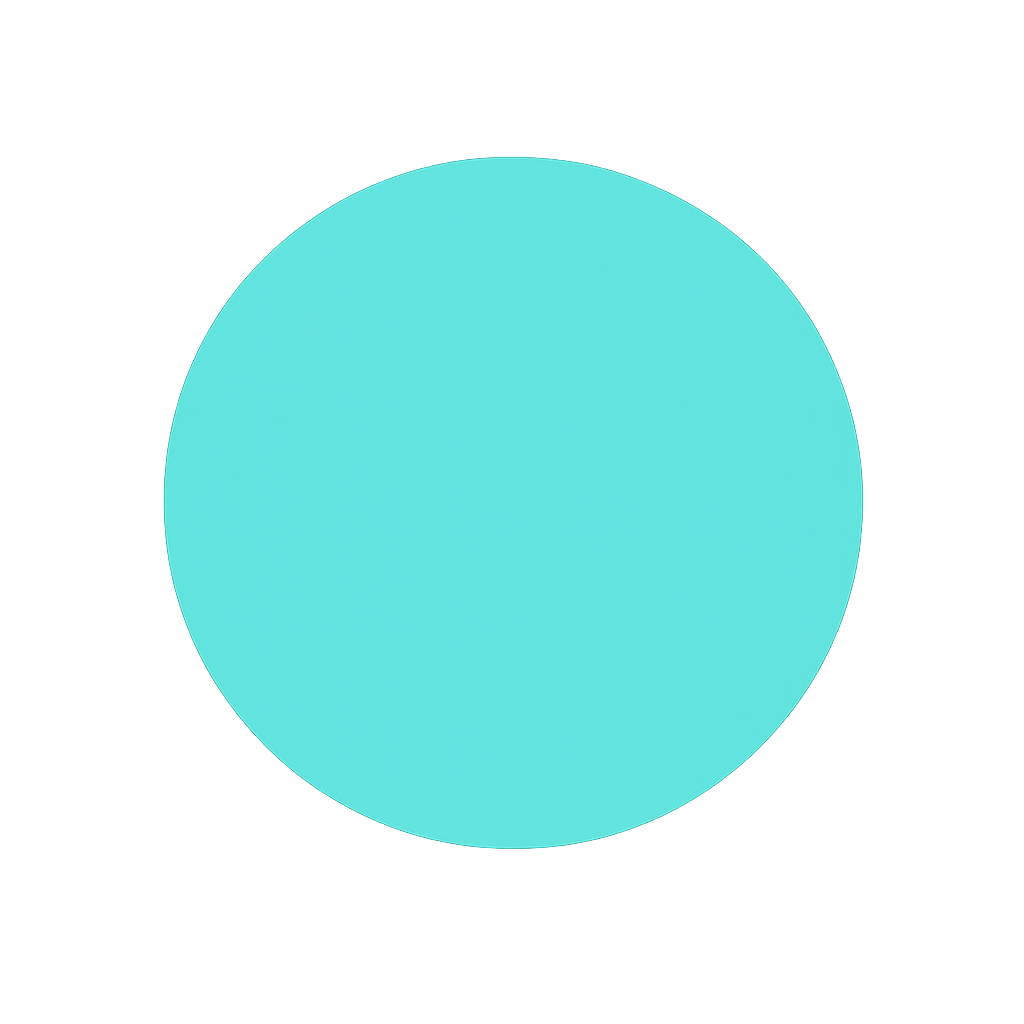
- 6月20日
- 読了時間: 31分
一人でいると、時間がどのくらい経ったのか忘れてしまう。赤い人がいなくなってから、眠っている時間が増えたような気がする。
ここは、寂しい場所だ。だって、とても静かだ。
そういえば、彼がいた時は、いつも音がしていた。とんとん、どんどん、何かを叩くような音。ここに来てからずっと聞こえていたあの音は、あの人がいなくなった途端、聞こえなくなった。
叩く音がしなくなった代わりに、キイキイ、と鳥の鳴き声がするようになった。声を追うと、百日紅の枝に一羽の瑠璃鶫がいた。こちらを見て、しきりに首を振っている。愛くるしい仕草だが、どこか不気味だ。
いつの間にか、ぶかぶかだった服の裾から手や足がはみ出すようになり、髪が見えるところまで伸びてきた。自分を映すものがないので知らなかったが、伸びた髪はあの人と同じ金色をしていた。服の色も同じだと気付く。視界に入る本を持つ手や丈の短い裾から伸びる踝に、時折ドキリとする。
いつも傍で見ていたあの人の手足に、似ている気がする。
手入れしなくても美しい庭を歩く。花を嗅ぎ、水に触れ、小さな生き物と徒に戯れる。あちらこちらに開きっぱなしの本が置いてあるので、手に取り読み耽る。いつ目覚め、いつ眠ったのかも分からないまま、漫然と時は過ぎていく。
気まぐれに現れては消える本を何度も読み終えて、庭園の花の数さえ分かるほどの時が流れる頃、扉から少女が現れた。
十歳くらいだろうか。長い金の髪と透き通るような碧の瞳をした、愛らしい、お人形のような少女。
彼女をこの目に映した瞬間、洪水のようにいろいろなことが思い出され、全てを理解した。
『そのうち、思い出すよ。いいことも。悪いことも』
ああ、そうか。この人が鳥籠の持ち主だったのだ。
―――そして、僕の会いたかった人。
あどけなく笑い、目を輝かせる少女と一緒に庭園を散策した。夢の中とはいえ、こんな残酷なことはない、と思った。美しく、優しく、寒い朝に張った氷のように壊れやすい、奇跡のような時間だった。
少女が出て、扉に錠が落とされた。その音がやけに大きく、何かの宣告のように耳に響いた。
――どんどん、どん。
いつの頃からか、またあの耳鳴りが聞こえ出した。叩くような音。扉から聞こえるらしい。強く、速く、弱く、遅く。ずっとずっと、まるで、誰かを呼んでいるようだ。
それから、子どもが現れた。少女と同じ年頃。ぶかぶかの、薄い青色をした服を着ていた。
その姿を認めて怖気立つ。
金の髪と、不思議な色の瞳。襟ぐりから見える細い金属の鎖。そして、その声。全てが一本の糸のように繋がる。この子どもが来たということは、きっともうすぐ、その時は来る。
「ここは、天国のような所ですね」
無邪気な顔でそう告げる。何も知らない小さな頭を撫でる。
……こんな風に、誰かに触られたことはあったのだったか。覚えていない。小さな僕は、頭を撫でられて嬉しそうに頬を緩ませた。
――どんどん、どん。
気が付くと赤い服を着ていた。この服も、知っている。服の釦や金具に髪が絡まりぷつぷつ千切れた。そういえば、随分髪が伸びた。
小さい僕が、別れの餞別にペンダントをくれた。首を飾ると、しっくりと馴染む。まるで、パズルの最後の一欠けのように。何も知らない子どもを置き去りにして、扉の前に立つ。我慢強い子どもだが、別れが寂しいのか追い掛けてきた。ズシャ、と音がしたので振り向くと、小さいのが転んで顔を上げている。その顔は痛みではなく、孤独に怯え強張っていた。別れの言葉を告げる。子どもは必死に手をつき起き上がろうとした。構わず扉に触れると、極の等しい磁石のように自然に開いた。今まで、押しても引いてもびくともしなかったのに。
どうやら、このペンダントが扉を開く鍵だったようだ。
扉が開き、現れた人物に戦慄する。知っている。僕は知っている。
この男を、どうして忘れていられたのか。
「迎えに来た」
彼は僕を見て、とても嬉しそうに、そして悔しそうに笑った。生気に溢れ、理性に輝く隻眼で。
「スレイン・トロイヤード」
ああ、そうだ。それが僕の名前だ。
ねっとりと血に濡れた手が差し伸べられる。その手を掴む。手を引かれ、走り出す。
階段を駆け上がる。知っている、これは十三段しかない。今何段目だ。
「この先は処刑台だ」
「知っている」
「手を離せ、逃げろ、でないと…」
でないと、とても悪いことが起こる。
何だったか、とにかく取り返しがつかないことが。
「嫌だ。君は生きるんだ。僕と一緒に行こう」
「駄目だ、離せ、撃たれ――」
――パン。
「界塚…」
撃たれた。ああ、そうだ。いつもそうだ。
「………誰が…?」
血に染まる体を白い手に抱えられ、断頭台が近づく。こいつらじゃない。こんな顔のない連中じゃない。あいつを撃ったのは。
ぎらつく刃を見上げる。映り込んだ僕は顔も、服も、何もかも赤い。
縄の張る音。揺れる視界。
また終わる。
こんな時に、鳥籠に残してきた小さいのを思い出す。
あいつ、殺してあげればよかったな。天国だと言っていたし。
……今度覚えていたら、殺してやろう。
――ヒュッ。
――キイ、キイ、キイ。
青い鳥が鳴く。
――……ここは?
「ここは…」
噎せ返るような薔薇の香りがする。体を起こすと、赤、白、黄の薔薇が鮮やかに目に飛び込んできた。立ち上がり、ぐるりと周囲を見渡す。
丈の低い緑の木々と、鮮やかな花々。薔薇だけではない。百合、マリーゴールド、デイジー、牡丹、菫にラベンダー、桔梗、杜若、ポインセチア……。
『わたし、知っているわ。この場所の形。絵本で見たのと、そっくり』
『チルチルはミチルと、青い鳥を探しにいくの』
『また来るわ。あなたに会いに』
――ガシャン。
彼女は黄金の長い睫毛に縁どられた瞼を開く。大きく息を吐き、小さいがスプリングの効いた優雅な長椅子で上半身を起こした。小さな頭に似合わない無骨なヘッドマウントディスプレイを外し、立ち上がる。ピンヒールの硬質な音。青白い光に満ちた円柱を見上げる。
「また、帰ってきてしまったわ」
『あなたを愛しています』
『赤い薔薇の、花言葉』
「…もう会えないなんて、寂しいことを言うのですね」
暗い部屋で、彼女は呟く。それはぷかぷかと、重さがないように青い水に浮いていた。
タンクの中で漂う、節くれだった手を外側から撫でる。手元のモニタには、眩しすぎる映像がチカチカと映し出されていた。音声はヘッドセット越しにしか聞こえないが、彼女には彼が何を言っているのか、全て分かる。なぜなら。
繰り返される同じ言葉を、もう飽きるほど聞いたから。
「早く、もう一度会いたい」
――ピッ。
無神経な電子音で、扉が開く。彼女の背後から通路の光源が差し込み、薄らと部屋中に沈殿していた影が輪郭を濃くした。戸口が作り出す影法師が部屋の主に来客を知らせる。
「青い鳥を、捕まえたつもりですか」
冷たく、抑揚のない声が鼓膜を震わせた。彼女は懐かしさでほろりと笑う。
「……ええ」
目の前のモニターに映し出された色鮮やかな映像に意識を戻す。鳥籠に、青い鳥が一羽。そして、人の姿の籠の鳥。
コポコポと、水を循環させる音。
絶え間なく続く、電子機器のノイズ。
招かれざる客が、一歩、二歩と彼女に近づいた。
「知っていますか? 青い鳥は、籠に入れるとだめになってしまうんですよ」
その言葉に、彼女は振り返る。軽やかな笑い声が、暗い部屋に鈴のように転がった。昔と変わらない、あどけない所作。花のような笑顔。
「あら、それはお話の中のことでしょう」
黄金の豊かな髪を高く結いあげて、昔より大人びた色の濃いドレスを着ている。装いに不釣り合いの少女めいた表情と仕草に、来訪者の胸が鈍く痛んだ。
「貴方が、それを言うとはね。アセイラム女王」
「お久しぶりです。界塚伊奈帆さん」
少女のように若々しく輝く美貌と、穢れない神々しい微笑み。冷たい光が支配する無機質な室内で、彼女の姿がホログラムのように浮かび上がる。伊奈帆は、彼女の後ろに設置されたアイソレーションタンクを見上げた。
閉じられた世界で、終わらぬ夢を見る人。
「最後にお会いした時には、ゆっくりお話しすることもできませんでしたね」
月面基地での邂逅を言っているのだろう。伊奈帆は小さく頷く。あの時はアナリティカルエンジンが勝手にぺらぺらと喋り出して、後で頭を抱えたものだが。
それも、もう昔のことだ。
「もう十五年になります。お元気でしたか」
そう、時が流れた。かつて少女であった女性は、過ぎ去った年月に何を思うのだろう。
「最近は、地球へ行くことも少なくなりました。デューカリオンの皆さんも、お変わりはありませんか」
火星地球間の外交は、今や夫であるクランカインが取り仕切っている。女王陛下夫妻の間には、四人の子どもが産まれている。先日の地球訪問へは、クランカインに十二歳になる姉娘が同行し、大きなニュースとなった。火星の第一皇女は母親によく似た顔立ちで、瞳の色だけが父親と同じだった。
「地球で一緒に、鳥を見たのを覚えていますか」
伊奈帆は頷いた。アセイラムは懐かしむように目を閉じ、唇が美しい微笑みの形を作る。伊奈帆は彼女まであと五歩という所で立ち止まり、右手の中指と人差し指だけを伸ばした二指の敬礼をした。
「アセイラム女王」
「まあ、余所余所しい。あの頃のように、セラム、と呼んでくださらないのですか?」
母親とは思えないほど若々しく美しい目の前の女性は、記憶の中の少女のように頬を膨らませた。
「アセイラム女王陛下。……迎えに来ました」
伊奈帆とアセイラムは、しばらく無言のまま見つめ合った。ブウン、と普段は意識されないハムノイズがやけに大きく聞こえる。アセイラムは首を振った。
「……折角ですから、もう少し、お話ししましょう」
彼女は両手を広げて、ようこそ、という風に膝を折った。優雅な仕草で首を傾げる。完璧な動作だが、表情はどこか歪を生じさせていた。感情と行動のアンバランスさを、伊奈帆は手の込んだマリオネットのようだと感じた。
「ここは、秘密の場所なんです。お客様なんて初めてよ」
彼女は自身の背後を示す。タンクの下部に設置された台座に、青白く輝く球体が据えられていた。台座はタンクと繋がれており、光がタンクの中の液体に光を通す。優しく、慈しみを存分に込めた手つきで彼女は球体を撫でた。
「このアルドノアドライブは、私が起動しました。私が死ねば、停止します」
青い光は、アルドノアの輝きか。伊奈帆は合点して、タンクの中に浮かぶ人間を見上げる。
道理で、あれから年を取っていないわけだ。
「そのアルドノアの能力は?」
アセイラムは、分かっているくせに、と眼差しに浮かべて伊奈帆を見上げた。くすくす笑い出し、アルドノアドライブを撫でた手が空で翻る。バレリーナのように軽やかにステップを踏み、夜色のスカートの裾が広がった。暗闇と踊るように、艶やかなスカートが黒に溶ける。
「夢を見せるのです。その夢が美しいほど、安らかなほど、意識は現実から乖離していきます。ご覧になりますか?」
彼女の軽やかな手が一つのモニタを伊奈帆に示した。伊奈帆は立った場所から目を凝らす。小さな画面には、花で溢れる豊かな庭が映し出されていた。
「花が咲き乱れ、緑豊かな美しい庭園。青い空には青い鳥が飛んでいます。天国のような美しい場所」
歌うように彼女は語り、舞うように手を開く。伊奈帆は、この冷たい部屋で、青い光を浴び孤独に佇む彼女の姿を想像した。
「伊奈帆さん」
ぴたり、と動きが止まり固い声が狭い部屋に響く。ここはとても狭い。アイソレーションタンクからごちゃごちゃ繋がる機械と嵩張る調度品に反響し、彼女の声は硬度と重みを増したようだ。
「迎えに来た、と仰いましたね」
伊奈帆を映す瞳の色は、翳って見えた。アセイラムは口を大きく動かし、絞り出すように一語一語をゆっくりと発声する。
「答えは、ノーです。スレインは、渡しません」
彼女はタンク脇のソファの上から、黒く無骨な機械を両手で持ち上げた。長いコードが数本、タンクに接続されている。
「これが何か、分かりますか?」
何も言わない伊奈帆にぎこちなく笑い、アセイラムは続ける。美しい声が流れる水のように淀みなく紡ぐ。まるで、恋の詩のように。懐かしい歌のように。告解室で繰り返された懺悔のように。
「私は夢の中で、こっそりスレインを訪ねるのです。扉は、勝手に開きます。夢の中の私に今の記憶はなく、幼い少女の姿をしています。スレインと出会った頃の私。その私は、花園で出会うスレインが誰なのか分からないのです。スレインはもう大きな、青年の姿をしていますから。スレインは、私に会うと現実を思い出すのでしょう。スレインは私を悲しそうに見つめます。彼に別れの言葉を告げられ、扉を出ると鍵が掛かってしまって、押しても引いても、絶対に開きません。そこで私の夢は終わり、現実へ戻って来てしまう」
彼女は溜め息を吐き出した。
「しまった、といつも思います。どうして扉から出ちゃうのかしら」
アセイラムは手に持った機器を置いて、モニタを再度掌で示した。
「夢の中の様子は、こちらに映し出されます」
白い指が画面の中の青い服の青年を指さす。彼は何かを見ている。画像がズームバックして、彼の視線の先にあるものが分かった。大きな扉だ。
「扉の外にいるのは貴方です。伊奈帆さん」
ヘッドセットのスピーカーから、扉を叩く音が聞こえるのです。大きな音で鳴りやまないので、もう、これを着けるのをやめてしまいました。そう言って彼女はスカートの裾を持ち上げ、ソファに座った。伊奈帆の正面には、小さなモニタと、アルドノアドライブと、アイソレーションタンクが並んでいる。
遮るものは何もない。
「貴方は扉を開けようとする。でも、決して開きません。扉は、スレインにしか開けることはできないのです」
伊奈帆はモニタの映像を見た。スレインのいる場所が変わっている。扉は見えなくなり、白い長椅子に座り本を読んでいた。青い小鳥が一羽、ベンチの上で羽を広げ、ちょこちょこと足を動かしている。スレインは本を閉じて立ち上がった。歩き出すスレインを追いかけて、青い小鳥が慌てたようにベンチから飛び立つ。
あることに気付き、伊奈帆は目を瞠る。やはり、ない。おかしい。あれは、どこにあるのだろう。
「その夢でも、もうすぐ赤い伯爵服を着たスレインが扉を開けるでしょう。伊奈帆さんはスレインの手を引き走りますが、道は処刑台につながる階段しかありません。あっという間に登りきります。貴方は銃弾に倒れ、貴方を失ったスレインは断頭台で首を落とされるのです」
私が夢から覚めた後の事は、何度見ても嫌な気分です。スレインの首が胴から離れて、血だまりの中をごろごろと転がっていくのです、と。彼女はソファに肘をつき思い切り顔を顰める。
「スレインは生きている」
アセイラムは顰めていた顔を綻ばせて、嬉しそうに伊奈帆を見た。笑う彼女の顔は昔と変わらず美しい。表情だけが、微かな憂いを帯び年月を感じさせた。
「そうなのです。また、あの庭園にスレインが現れます。幼い姿をしています。その子は成長して、私と出会い、貴方に手を引かれ、またこの庭に戻る」
「もう、何回目ですか」
伊奈帆が冷たく聞くと、彼女は困ったように眉を寄せた。
「さあ。もう、数えることをやめましたから」
惑星間戦争から数年を経た頃、スレインの処遇について大きな変化があった。
極秘施設を解体し、秘密裏に軍で有効利用しようというのだ。軍人として抜群に腕が立ち、頭脳明晰で度胸もある。その後の取り調べや調査で戦争時の内情が明らかになるにつれ、彼の義理堅く、損得を越えた行動力もただ処刑するには惜しく思われた。その頃には、スレインは従順で礼儀正しい模範囚と認識されていたし、監視役の伊奈帆との関係はかなり親しい友人程度、と軍内で評価されていた。
そういう状況を鑑みた上層部から、ひとまず伊奈帆が彼の身柄を預かり、任務のサポートに同行するよう達しがあったのだ。アナリティカルエンジンを外し視界が利かない伊奈帆の頭脳を前線で活用するためでもあった。サポート役の適任者が見つからず、数年が経過していた。
要するにスレインは、二十四時間体制のボディーガードとして、伊奈帆と同居生活をすることになった。
その生活は、それなりに良好だったと伊奈帆は思う。口論や喧嘩じみたやり取りはあったものの、彼との暮らしは穏やかだったし、楽しくもあった。自分たちには、共有した過去と語るべき未来があったから。
数か月間の共同生活にピリオドを打ったのは、一発の銃弾だった。
「最後の地球訪問で、極秘で要人警護の任務に就いていた僕を撃ったのは?」
アセイラム女王陛下夫妻は、子どもと地球を訪問した。身辺警護のため火星・地球双方の厳戒な警護体制が布かれた。伊奈帆たちは六歳になる第一皇女の近接保護部隊に配置され、記念式典の会場を見下ろす高層ビルの屋上にいた。
「その銃弾は、僕を庇ったスレインの胸に命中した。意識不明の重体」
スレインは伊奈帆の目の前であっけなく倒れた。伊奈帆はこれまで積み上げてきた何かが、誰かの都合で理不尽に崩れ去るのを見た。
これからって時に。やっと、生き始めたのに。
「すぐ軍の病院へ搬送された。数時間後、任務を終えて僕が駆けつけた時にはもういなかった」
アセイラムはソファに体を預けたまま、伊奈帆の言葉を待っている。タンクの中、逆さに降る雪のように舞い上がる気泡を、伊奈帆は両眼で追う。細い帯のように細かな気泡が、ちらちらと彼の髪を掠めて揺らした。
それから六年。少尉だった伊奈帆の階級が中尉になり、大尉を経て、少佐になるまでの時間。
ずっと探していた。そして。
「やっと見つけた。生きていて良かった」
伊奈帆は水の中の青白い顔を見上げる。瞼が固く閉じられて、目が見えない。地球を象徴するような瞳の色。見つめられると吸い込まれそうな。一緒にいた頃は見蕩れたことに照れて、大げさに目を逸らしたものだった。
「よく、ここに来ることができましたね。伊奈帆さん」
アセイラムは億劫そうに言った。伊奈帆がここにいるということは、彼女のした事、考えた事を全て了解していることを意味し、それは彼女にとって心の内側を検められることに等しかった。
「もっと早く来るべきだった。全て仕組まれていたとは、信じられなかった。………信じたくなかっただけかもしれませんが」
アセイラムが草臥れた顔で、力なく首を振った。
「この行動は、未来を棒に振るとは思いませんか」
この女性も、そんな俗っぽいことを言うようになったのだ。アセイラムがソファから身を起こし、伊奈帆の隣へ静々と歩み寄った。
二人で肩を並べ、青い円柱を見上げる。まだ少年と少女だった頃、二人で肩を並べた遠い記憶が脳裏に甦る。
年を取った。世界を知った。人間を、知った。あの頃の二人の間に流れる清冽な空気は過ぎ去り、もう戻らない。鮮やかに輝く思い出と、暗く冷たい現実が同時に見えて吐き気がした。
現実と夢を分かつ、ガラスの丸みに触れる。冷たいがどこか生々しい、お湯の冷めたバスタブのような感触だ。
「夢の中で」
アセイラムが囁いた。伊奈帆の手の横、彼女の手もガラスに触れた。
「いつも貴方を撃つのは、誰だと思います? 伊奈帆さん」
伊奈帆は横目で視線を送るが、目が合うことは無かった。彼女はスレインを見たまま言った。
「私です。貴方の胸に、銃弾を撃ち込むのです」
白い手が滑り落ち、モニタの前のパネルの上で止まる。指先が、一つのキーをくるくる撫でた。華やかに色づいた唇が震え、このスイッチで、と自嘲するように口角を引き結ぶ。そんな笑い方は、この人には似合わない。そう思い、伊奈帆は憂う横顔を眺めた。
「嫉妬かしら。取られるが嫌なのですね」
「スレインを愛していますか」
こんなことを、照れずに聞くことができる年になった。伊奈帆の言葉に、彼女は静かに頷いた。
「ええ。とても。誰かに取られたくありません。私の、大切なひと。大切な、思い出」
伊奈帆は瞳を閉じる。瞼の裏に浮かぶのは、色褪せぬ記憶。
どこまでも青い空と波立つ海。
――こんなに空が青いなんて。こんなに海が輝くなんて。
飛び交う白い鳥の群れ。
――鳥なんて初めて見たわけじゃないのに。ずっと見ていたいと思った。
強く吹き付ける潮風。
――辛くて粘つく潮風は、嫌いだったはずなのに。
翻る、白いスカート。
――その下から覗く足首は、もっと白かった。
汚いものや醜いものなんて、映したことがないに違いない美しい瞳。
――いつもまっすぐに合わされる眼差しは逸らすこともできなくて。
彼女は言う。白い頬を赤く染めて。美しい瞳に空と海の青を映しこんで。夢見るような声で。
『スレインの言った通り』
その手の中には、清らかに光る銀色のお守り。
それも、もう思い出だ。その美しさも、輝かしさも、胸を焦がす感情も。
伊奈帆は両目を開いて、現実に対峙する。タンクに触れたままの右手を握りしめる。自分の爪が掌に食い込む。手の甲の血管が浮き上がる。汗がこめかみを伝った。
「過去は変えられない。貴方は、選択したはずだ。それを無かったことにはできない」
何かを選ぶということは、何かを捨てるということ。あの戦争の最中、誰もが手を伸ばした。守りたいもの、焦がれたもの、失いたくないものに。その手に、何も掴めなかった人もいた。掴んだけれど、放してしまった人も。掴んだものが、違うものだと気付いた人もいたろう。中には、もともと持っていたものを手放した人もいただろう。しかし、その手に、何かを掴み取った人もいたはずだ。
伊奈帆は、スレインの手を掴んだ。それを後悔したことはない。
彼女は、違うのだろうか。今になって、伸ばした手が過ちだと気付いたのだろうか。手の中にあるものが、分からなくなったのだろうか。
「現実で会うことが許されないなら、せめて夢の中で会いたい。子どもの頃のように、笑い合いたいだけ。それはそんなに悪いことなのですか」
過ぎ去った思い出の中で、もう一度。何も知らなかった二人に戻りたい。アセイラムの頬を涙が幾筋も伝った。
彼女の泣き顔を見るのは三回目だ。伊奈帆は、今までで一番人間らしい泣き顔だと思った。
「スレインを救ってくれ。貴方はかつてそう願った。それは、今の僕の願いだ」
「夢は美しく優しい世界です。それは救いではありませんか」
「馬鹿なことを」
舌打ちをして、そう吐き捨てる。
伊奈帆は出会った時の、まだ一人の少女であったアセイラムを想った。子どもだった。純粋だった。そして残酷だった。その優しさは独り善がりで支配的で、溢れんばかりの愛情は誰か一人に注ぐものではなく、万人に振りまくもの。彼女の瞳は、いつも遠い未来と輝く希望に満ちていた。歪で孤独で、強く輝かしい少女。少年だった自分は、そんな少女が好きだった。その光に恋をした。
容赦のない現実と迷いと後悔渦巻く胸中が彼女を弱く、狡くした。しかし、今になって人間らしい愛情を知ったのかもしれない。嫉妬するのは、愛しているからだ。でも伊奈帆は、彼女のお願いを今度ばかりは聞くことはできない。
「僕には、悪夢にしか思えない。アセイラム。夢の中で、スレインを何回殺せば気が済む? 何度だって言ってやる。スレインは生きてるんだ」
アセイラムはスカートから銃を取り出し、流れるような滑らかさで伊奈帆の左胸に銃口を押し付けた。
「私を、どうしますか。撃ちますか」
にっこり笑い、首を傾げた可愛らしい仕草。
「撃つならどうぞ。私のほうが早く引き金を引くでしょうけれど」
ころころと笑う口元を見る。薄紅に色づく、左右対称に弧を描く美しい唇。
「私が死んだら、スレインも死にます」
狂っているのだろうか、とも思った。しかし、その瞳が透明に澄みきっているのを知り、伊奈帆は失われたセラムの欠片を瞳の中に探した。
「そんなことはしない」
アセイラムの瞳から涙がこぼれ落ちた。頬を伝う涙は、光に照らされ青く輝いた。悲壮な、美しい顔で彼女は指先に力を込める。
「それでは、私が貴方を撃ちましょう。夢の中のように」
「迎えに来た」
開いた扉から、男が手を伸ばした。その顔と名前に、忘れていた膨大な記憶が呼び起される。名を呼ばれ、反射のようにその手を握る。
あれ。
おかしい、と思った。だって、触れた手があたたかい。そして更におかしな事に、握る手に血は一滴も付いていなかった。それに――。
考える間もなく、強く手を引かれ駆け出す。つんのめりそうになりながら、濃紺の裾がはためく背中を追う。
ああ、また。
デジャヴにほっとする。そうだ、これは何度も見ている夢なのだ。見覚えのある大理石の白い階段。踏み出す一歩一歩を、走っているはずなのにゆっくりと感じた。全部覚えているはずなのに、その時が来ないと思い出せない。焦りで余計に混乱する。今、何段目だ? この階段は、ええと、どこに続いているのだったか。なんだか良くない所だった気がする。
脳裏に閃く、強すぎる光。
「この先は駄目だ……」
痛む頭を振り呻くように言うと、立ち止まり、力強く手を握られた。
やっぱりおかしい。なんだか、いつもと違う手じゃないか。いつもはもっと小さくて、こんな熱くなんて無かったような――。
「大丈夫。上手くいく」
にい、と笑う顔を見て、ああ、と違和感の正体に気付く。そうだ。こいつ、違う違うと思っていたら、今日は左目があるじゃないか。口を開くが何か言う間もなく、手を引かれまた走り出す。
汗が噴き出る。心臓がばくばくと命を食らうように蠢く。瞬きすると、ぎらり、とまた何かの光が閃いた。とても嫌な感じだ。
「駄目だ、お前は引き返せ。そうでないと――」
言っても立ち止まらないし振り向かない。握られた手に力が伝ったのが分かった。
「大丈夫だ。一緒に行こう」
振り解こうとするが、とても強く手を握られていて逃れられない。立ち止まろうとしてもすごい力で引っ張られる。
いけない、駄目だ。この先は良くない場所だ。十三段目に足が乗る。
「お待ちなさい」
声が聞こえた。伊奈帆が立ち止まり、スレインは伊奈帆の背にぶつかった。金縛りのように足が動かせない。
ああ、そうだったのか。十三段目でいつも僕らを撃つのは。
「姫様……!」
白く可憐なドレスを着たアセイラムは、少女の顔で伊奈帆を睨んだ。両手は、膨らんだドレスのスカートの上で軽く握られている。何も、持っていない。
「伊奈帆さん、どういうことですか」
伊奈帆は、その視線を見据え不敵に笑った。スレインはアセイラムの引き結んだ口元を無言で見つめる。
「銃がないでしょう。僕を止めることはできませんよ」
そしてスレインの手を引き走り出す。立ち尽くすアセイラムの横を通り過ぎる刹那、彼女が顔を上げて叫んだ。
「スレイン!」
思わず振り向くスレインに、伊奈帆は鋭く言う。
「そのペンダントを」
「え?」
伊奈帆がスレインの首で揺れる銀の鎖を握りしめた。
「ペンダントを、くれる?」
伊奈帆の熱い手の温度を感じながら、スレインは鳥籠の中に残してきた小さい自分を思い出した。これは、きっと。
でも――。
「やる」
強く頷くスレインに、伊奈帆はありがとう、と言い鎖を引き千切った。ペンダントを持った手を振りかぶる。
「彼女に、あげるよ」
「ああ」
伊奈帆がペンダントを投げた。カンカン、カン、とアセイラムの足元に転がり、彼女は膝をつき茫然とそれを拾い上げる。両手の中でそれは青い鳥に変わり、小鳥は数度震えて動かなくなった。彼女は死んでしまった鳥を胸に抱く。
「スレイン…」
嗚咽交じりの痛ましい声が聞こえる。伊奈帆がスレインの手を強く引いた。
「行くよ」
スレインは蹲るアセイラムと伊奈帆を交互に見た。困り果てた声が出る。
「姫様が、呼んでる」
何度もスレイン、と呼ぶアセイラムの姿に動き出せずにいるスレインの肩を、伊奈帆の両手ががっしり掴んだ。痛いくらいに握られて、スレインが小さく呻く。伊奈帆はスレインの顔を覗き込んだ。
「彼女が呼んでいるのは、君じゃない」
そして踵を返し、駆け出す。その手に行く先を委ねる。
そうか、僕じゃないのか。
彼女の胸に抱かれた青い小鳥。
……小さいのがいなくなってしまったな。あの庭園は、もう空っぽだ。
スレインは足を動かし、我に返って周囲を見渡す。少し高い位置に伊奈帆の背中。また階段だ。
おかしいな、階段は終わったはずなのに。
いつの間にか、白い大理石の階段は、金属音を鳴らす非常階段に変わっていた。カンカン、カン、と踏むたびアルミの揺れる階段の踊り場を何度も折り返す。風が吹いている。
「界塚……。これは、いったい」
「悪い夢だ。はやく醒めよう」
階段を上り続ける。強い横風に吹き飛ばされそうだ。眩しくて目が開けられない。長い。終わりがないようにさえ感じる。風鳴りがする。今、とても高いところにいるらしい。
「天辺だ」
伊奈帆が言って、強く手を引っ張った。スレインはふらつきながら最後の一段を踏み出す。
風が通り抜ける。眩しい光に包まれ、反射的に目を瞑る。
光。こんなにも眩しいものだったのか。
日の温度を瞼に感じ、目を開ける。
――青。
――があ、があ、があ。
――潮の香り。
――頬に辛い風。
――きらきらと輝く波間。
――晴れ渡り、どこまでも続く空。
――そして、隣には。
ビ―――――。
耳に痛いほどの電子音が室内に反響した。アセイラムは伊奈帆の胸に銃口を向けたまま、きょろきょろと周囲に目を走らせる。タンクの中、ごぽりと大きな気泡が発生し彼女はそれを見た。伊奈帆は彼女の視線を追う。どうやら、上手くいったようだ。
青白い光の中で、スレインの瞳が開く。ゆっくり三度瞬きをした。指先が微かに動き、それを見たアセイラムは銃を取り落としモニタに顔を近づける。慌ててパネルを操作するが、手応えがなくバン、と両手をキーに振り下ろす。衝撃に痛むだろう指を握った。肩がわなわなと震えている。
「伊奈帆さん、一体何を…」
伊奈帆は床に落ちた拳銃を拾い上げた。ヴァ―スの刻印がある白い銃。
「ここに来る前、回路に潜入してプログラムを書き換えた。…夢から醒めたみたいだ」
伊奈帆は銃を構えた。アセイラムが体を強張らせ目を瞑る。
トリガーを引く。
白い銃口から弾丸が飛び出し、衝撃波が室内に響き渡る。
一回。
二回。
三回。
四回。
五回。
六回。
伊奈帆は、銃弾を全て吐き出した銃を水浸しの床に放り投げた。耳障りな音を立てて回転しながら、それは部屋の隅へぶつかり止まった。
「あ、アルドノアドライブが…」
アセイラムが膝から崩れ落ち、床に座り込む。滑らかなドレスが水を吸い、重そうに床にへばり付いた。粉々になったアルドノアドライブの破片が発光し、部屋中が青く染まる。伊奈帆は服が濡れ汚れるのも厭わず、粉々のタンクの中に両腕を伸ばす。
「スレインは目覚めた。アルドノアドライブが停止しても問題ない」
ガラスの破片で細かい傷を無数に作りながら、伊奈帆はスレインをタンクから引き摺り出した。メディカルスーツが水を含み、意識を失い弛緩したスレインは重くて手古摺るが、伊奈帆は器用に担ぎ上げアセイラムに向き直る。
「悪いけど、スレインは連れて行く」
さっと踵を返し扉を出て行こうとする伊奈帆に、アセイラムが手を伸ばした。
「待って!お願い、行かないで…」
伊奈帆は振り返らず、足を止めた。
「人は思い出の中では生きられない」
激しくしゃくり上げる声。彼女は、これまでの人生でこんなに泣いたことはあったのだろうか。
「だって、もう、会えないなんて…」
誰もが一人で死んでいかなくてはいけないなんて。
なんて寂しいんだろう。なんて悲しいんだろう。どうして、人は過去に戻ることはできないんだろう。失われたものを、取り戻すことができないのだろう。
「約束だから」
優しい声にアセイラムは息を止め、見つめる。青白い光の中、黒いドレスの彼女の顔と手だけが幽霊のようにぽっかり浮かび上がった。振り向いた伊奈帆は、暗い室内に向け眩しそうに微笑む。
「セラムさんとの約束だ。もう、いないけれど」
蒼白になるアセイラムから視線を外し、伊奈帆は境界線を跨ぐ。
「伊奈帆さん、スレイン!待って!」
伸ばす手は届かない。手放したもの。掴めなかったもの。
こんなに遠くに行ってしまうなんて。
「さようなら。アセイラム女王。お健やかに」
ピ、と電子音がして扉が閉まる。
「……界塚」
「気が付いた? まだ寝ていた方がいいな。かなり揺れるから」
シャトルの座席にベルトで固定していると、スレインが目を覚ました。座席を調整しつつ、伊奈帆はスレインに微笑みかける。スレインは伊奈帆をぼんやり眺めた。暗い部屋では分からなかったが、顔色が酷い。やつれた頬を触ると、冷たかった。
「…ここは?」
スレインの声はガサガサに掠れていた。ようやく聞き取れるくらいの声で言い、大きく見える目がぐるりと周囲を確認した。シャトルの計器類が小煩い音を立てている。
「ここは揚陸城だ。これから地球へ帰る」
伊奈帆が言うと、スレインはそうか、と言って目を閉じた。ここは刺激が多すぎる。ずっと現実から隔離されていた彼の肉体と精神が、発射と大気圏突入に耐えられればいいが。
仕方がない。リスクは自由の代償だ。
数分後、伊奈帆がシャトルを発射させた。スロットルレバーを操作しつつ、遠ざかる揚陸城に意識を向ける。
そういえば、アセイラムはなぜ設備の整った火星や月ではなく、揚陸城にスレインを幽閉したのだろう。伊奈帆は考えても仕方がないと思いつつも、取り留めなく思考を走らせる。
一人になりたかったのだろうか。二人きりになりたかったのだろうか。
その両者に、どれほどの違いがあるのだろう。
横目でスレインを見ると、ぐったりと目を閉じていた。意識があるのかはわからない。
「……別に、あのままでも良かったんだ。姫様のお心を慰めることができるのなら」
数時間後、月の破片漂う星の海を飛行していると、スレインが口を開いた。
彼なら、そうすることに何の後悔も躊躇いもないだろう。大きな岩石を鮮やかに避けつつ、伊奈帆は頷いた。
「そうかもしれないね」
操縦桿を操作する傍ら、スレインの青く痩せた横顔を見る。昔のままの、命の薄い、傷つきやすい儚い姿だ。その姿に胸を痛める自分は、彼よりずっと早く年を取ってしまったように思う。
「……姫様を悲しませてしまった」
目に見えない悲しみが、雪のようにスレインの周囲に降り積もる。俯く彼の首がひどく頼りなげで寒そうに見えた。
「……そうだね」
スレインは唐突に伊奈帆に体を向け、その勢いでベルトが骨に食い込み小さく呻いた。戸惑いを顔中に浮かべ、言葉を探している。
「………どうして」
どうして、か。伊奈帆は考える。そして思う。言葉にするのは簡単じゃない。だって、スレインがいなくなってからここに至るまで、伊奈帆は自分の行動を自分にすら説明することができないのだ。
約束だから? 友だちだから? 命を救われたから? そんな言葉をいくら並べても、心のどこかがそれは違う、と文句を言う。そんな自問自答の最後に、いつも思い出す。海と空の青と白いドレスを。暗く寒い場所でこぼれ落ちた透明な涙を。
「……君が、いなくなるのは嫌なんだ」
銃弾が貫いて、崩れ落ちる体を支えられなかった。大量の血が流れて、連れて行かれた。そうして、スレインはどこにもいなくなった。
伊奈帆は、あの日のことを思い出す。ほうぼう探した後、家に帰った。暗くて冷たい部屋だった。照明のスイッチを入れ、重い足取りでそれぞれの部屋を見て回る。何か月も一緒に暮らしていたのに、まるで最初から存在しなかったかのように、スレインの私物は存在感がなかった。服も食器も、石鹸やシャンプーも、そこにあったものを適当に使っていたのだ。洗面所に入る。脱衣籠に放り込んだままの、丸まった寝間着と洗面台の歯ブラシを見る。居たんだよな、と誰もいない部屋で呟いた。
茶碗とか、お箸とか、パジャマとか。彼だけの特別なものを買えば良かった。どうして、そんな簡単なことをしなかったのだろう。毎日一緒に暮らしていたのに。
最低の気分でベッドに座り込んだ。そういえば、専用のベッドも布団も買ってなかったな。何となく、いつも一緒に寝ていたから。
肩を落としてベッドサイドを見ると、月明かりに照らされそれはきらりと光った。
慌てて手を伸ばす。それを触り、裏返し、翳して見る。間違いない。スレインのペンダントだった。
こんな大切なものを置いていくなんて。
その時、伊奈帆は決めた。
きっと、僕は君に辿り着こう。だから、どこかできっと生きていて。
「伊奈帆」
はっとして、顔を向ける。スレインがシートに体を預けて、モニタの中の小さな地球を見ていた。
「……お前が撃たれる夢を見ていた。どうやら、何度も何度も同じ夢を見ていたようだった」
スレインは思い出すように時折目を閉じて、小さな声で言葉を紡いだ。伊奈帆はじっと耳を傾ける。
「お前が僕を迎えに来て、一緒に階段を上るんだ。階段の先には断頭台がある。最後の一段を上りきる。そこで、お前は胸を撃たれる」
僕は首を落とされて、終わり。それを何回も何回も繰り返した。でも、さっき見た夢は違った。
そう言ってスレインは伊奈帆を見た。その眼差しは澄んでいた。あの日の面会室で見た瞳のように。頬を濡らした涙のように。
「長い階段を上りきると、青い空が広がっていた。ウミネコの群れが飛んでいて、海がきらきらと輝いていて…。匂いもする。海の匂い、肌に痛い風。地球の景色だ。………姫様が隣にいた。そこで目が覚めた」
滔々と語る声は優しく、語られる言葉は美しくて、伊奈帆は長い瞬きをした。瞼の裏に、その光景が見える。
あれは、確かにあったこと。
「あれは、お前の記憶か」
「まあね」
今は遠い記憶だ。まだ知らなかった。世界を。自分を。人間を。大人になるということを。人を愛するということを。
子どもの見た世界。それは歪で美しかった。
「……美しい記憶だ」
スレインが精一杯に微笑んだ。悔しそうで、悲しそうで、それでいて誰よりも幸福そうで、あまりに下手くそに笑うものだから、見ていて伊奈帆は涙が出そうになった。
美しい記憶。美しい思い出。でもその意味を、思いを、きっと僕たちは共有できない。
でも、それでもいい。君が生きているんだから。
「思い出は、いつも綺麗だ」
思い出が綺麗なのは、そこに痛みがあるからだと思う。痛みが、思い出を美しく彩るのだ。
あ、と思い出して、伊奈帆は自分の首の後ろに手を回す。
「……これ。忘れもの」
失くさないように、見つけたあの日からずっと首にかけていた。外して、手を伸ばしスレインに差し出す。彼は受け取り、首を振った。
「ああ。お前にやるつもりで、置いていったんだ」
「え、どうして?」
スレインはペンダントを手の中でころころと転がし、口を重そうに開いた。
「………なんだか、もうあの部屋に帰れないような気がしたから」
伊奈帆は何もない、寒々しい部屋を思い出した。たった一つ残された彼の私物だったもの。もしかして、形見のつもりで置いていったのだろうか。
「ねえ、今度海を見に行こうか。二人で」
突然の伊奈帆の提案に、今度はスレインが首を捻る。
「どうして?」
伊奈帆は思案する。
どうして。どうしてか。君の笑顔が見たいから、君の思い出がほしいから……なんて気障すぎる。言葉にするのは難しい。そんなことを考えながら、次々進行方向に現れるデブリを避け、操縦桿をリズミカルに叩く。
「さあ。でも、いいだろう? 理由がなくても」
その言葉に、スレインは声を上げて笑った。ようやく明るい笑顔が見られて、伊奈帆もほっとする。スレインは笑いすぎて目の縁に滲んだ涙を拭った。
「ああ。理由なんて、ない方が素敵だ」
いよいよ大気圏に突入する。
二人で大気圏を越えるのは二回目だ。そういえば、あの時も一緒に地球に落ちるのに理由なんてなかったな、と伊奈帆は思った。



コメント