And Blue Sky._2
- μ
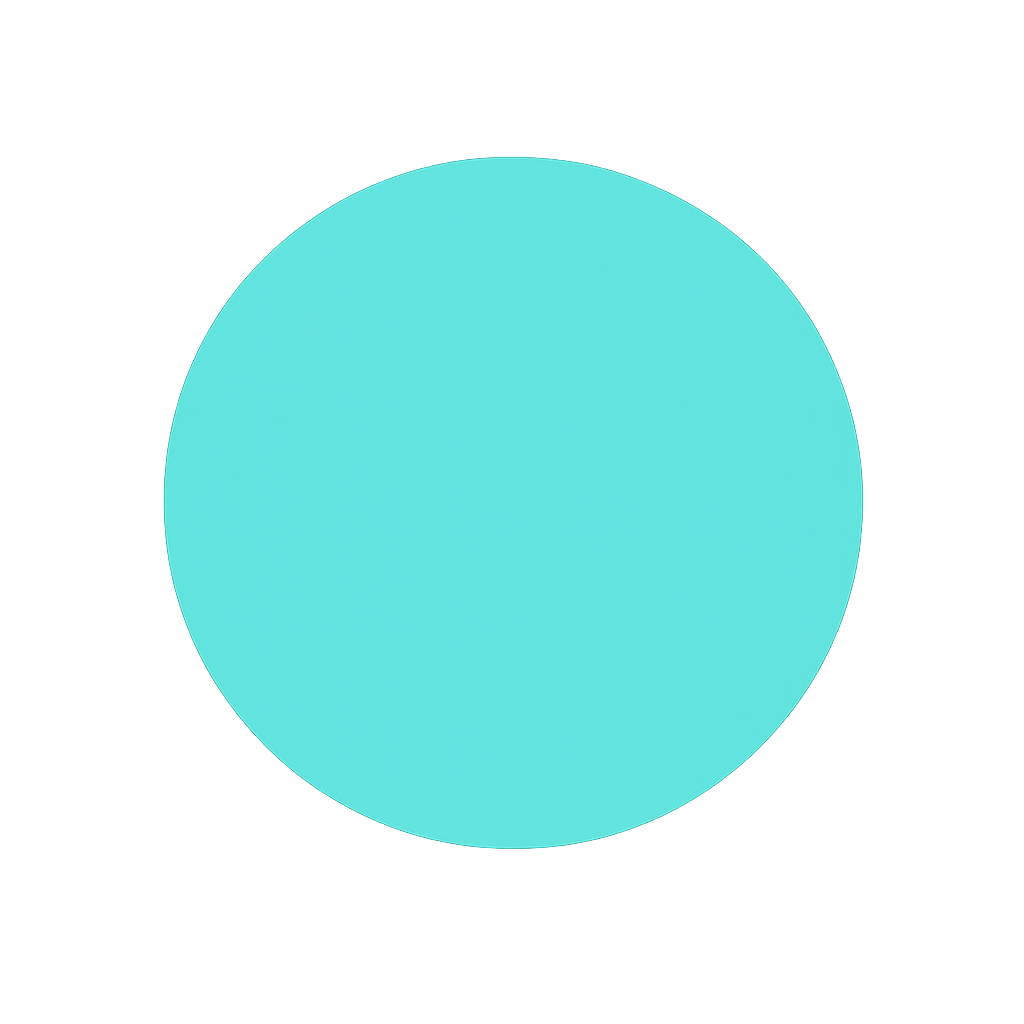
- 6月20日
- 読了時間: 54分
「……界塚伊奈帆は、どうかしたのですか」
面会が途切れ半年ほど経った頃、堪りかねてスレインは食事を配給する看守に聞いた。
彼とは、挨拶以外にも時々言葉を交わすようになっていた。収容当初から、戦犯である自分を気に掛けてくれていたのを知っている。看守はスレインを一瞥して、気の毒そうな顔で首を振った。
「……答えられない」
「死んだのですか」
ガシャン。
食器が割れるかと思うほど音を立て食事を置いた看守は、大きな靴音を立てて立ち去ろうとした。普段は穏やかで冷静な人物だ。スレインは意外に思い、界塚伊奈帆は、ともう一度聞いた。看守は口を閉じろ、と怒気を含んだ声で命じた。この看守の、このような感情的な声音は初めてだった。
「何も聞くな。君にそんな権利はない。……罰則があるんだぞ」
「……はい」
ばつが悪そうに立ち去る看守にの方向に顔を向けて見送り、スレインは立ち上がった。足元がふらつく。
食事が喉を通るとも思えなかったが、独房の簡素な椅子に座り、手探りでパンを掴んだ。機械的に口に運んで咀嚼する。喉の奥がそれを拒んで痙攣したが、水と一緒に飲み込んだ。
そういえば、ここ最近、食事に等閑になっていた。食物を摂取するのに、こんなに苦労するのは久しぶりだった。
食べろ食べろと言うが、ちゃんと食事をするのは、結構大変なんだ。特に、お前が来なくなってからは。
時間が掛かるかもしれないが、幸か不幸か時間は持て余すほどある。
どうせ、失うものも、得るものもない。
心なんてものは、もう何処かにやってしまって、見つからない。
だから、これからのことは全て、他にすることもないからだし、面倒とか、辛いとか、そんなこともない。退屈で、お前が来なくなったから。仕方なく、だ。
お前が来ないのなら、こっちにも考えがある。まず、この食事を全て食べ終える。スレインは嘔吐きつつ、界塚伊奈帆の小煩い顔を思い浮かべた。
伊奈帆が来なくなっても、スレインを取り巻く環境は、変わり映えしない。同じ場所。同じ時間。同じ人間たち。皆、繰り返される日常に慣れてしまった。
誰も、何も教えてくれない。当然だ。彼らには立場がある。自分は敵だ。なら、手段は一つ。
界塚伊奈帆のいなくなった場所で、スレインは辛抱強く自分を取り巻く人々が支配下に入るのを待ち構えることにした。
スレインは従順に、望まれるように、そして時折期待を持たせるように行動した。界塚伊奈帆の生死を確認するためだけに、心を売って(そんなものはとうに失われてはいたが)、体を投げ出し(それも、もはや別になんの痛みも伴わない作業の一つであった)、暗い地下でひっそりと生き延びた(別に、死んでも良かったのだけれど)。
職員たちは、いつの頃からか誰も訪れる者のないこの施設で、たった一人の囚人に飼い馴らされたようだった。
スレインにとっては苦痛しか伴わない生きる作業ではあったけれど、もう慣れた。ささやかな目的は、時折スレインの思考を窓の外へ向けさせた。
小さく四角い窓に顔を向ける。
界塚伊奈帆。
お前は生きているのか。それとも死んでいるのか。でも少なくとも、僕には死んだような気はしない。
それなら、もう少し生きてみよう。できれば、憎まれ口の一つくらい言ってやりたい。チェスだって、勝ち逃げされているんだ。
そして、界塚伊奈帆が消えたあの日から、一年と少しの月日が流れた。
その日も、スレインは看守の一人と寝ていた。彼らはあまりに無為にすごすこの場所で、自分たちの任務の意義を見失ったようだった。毎日数度のこの作業は、スレインの方から仕向けた事態であり、思惑通りではあった。
数年の付き合いでこんな罪人にも情が湧いたのか、施設の職員たちはスレインに酷いことをしない。暴力は微塵もなく、行為の最中には愛の言葉を囁く者もいた。驚くのは、毎度きちんと湯とタオル、着替えが与えられることで、当初スレインは火星とのあまりの違いに皮肉を感じたものだった。
火星では、罪を犯したわけでもないのに、地球人と言うだけで手酷い仕打ちを受けていた。大罪人になった今では、安全な場所で、衣服も、食事も、寝床も用意されている。一日数度行われる行為にも、特に感傷も感想もない。
最中にふと、我に返る。あの日触れた柔い頬や、固い癖のある髪。着こんだ服の下の硬い肉の感触を手が思い出す。額が、戦で硬くなった指先の強い力を覚えている。
――調子は?
いつだって同じことばかり聞いて。僕は、何て返していただろう。
どうしても知りたかった。界塚伊奈帆はどうして来なくなったのか。
嫌気がさした。気の迷いだった。それは当然だ。まともな人間なら、誰だって来なくなる。誰だって見捨てる。しかし、スレインは界塚伊奈帆のことを、もう、よく知っている。「また会おう」そう言って、ただで死ぬ男ではない。用意周到でしつこいあの男なら、たとえ死んでいたとしても、何らかのアプローチがあるはずだ。そういう男だ。
換気扇の風で、少し肌寒い。気怠い体を仰向けにして天井を見上げたスレインは、隣の裸の背中にぴたりと手を当て体を寄せた。この看守が、甘い男だと知っている。
「……界塚伊奈帆は」
スレインがその名を出すと、看守の背が震えた。彼にとっては英雄であった男の名をもう一度、唇に乗せる。
「界塚伊奈帆は、ずっと来ない。死にましたか」
そう囁いて、肩に手を乗せた。その手をゆっくり握られる。大きく、無骨な手だった。この看守は、よくこうして手を握る。他のどの部分よりも、手の形を覚えてしまった。
「……本当は、言ってはいけないんだが」
スレインと十も違わないだろう看守は背を丸めた。握られた手に力が入った。掌に、蛸がある。がさがさとした、乾いた熱い手だ。
「死んだよ。葬式に出た」
まだ若いのに、可哀想になあ。
ぽつりと、看守が呟いた。スレインは、広い背中に顔を埋めた。
「界塚伊奈帆の姉に、会うことはできませんか」
スレインは、特に入れ込んでいる職員の一人に聞いた。
腰を動かしていた壮年の男は動きを止め、彼の汗が腹の上に数滴落ちた。上がった息が平かになる頃、汗が胸にもう一滴落ちた。
「なぜ?」
「彼が死んだから」
体内で熱量が失われていくのが分かった。唐突に引き抜かれて、喉が引き攣る。解放された腰と体の重みでスプリングが軋んだ。
男は立ち上がり、そのまま何も言わずに服を着て扉から出て行った。スレインは扉が閉まると腹這いになり、固い枕に顔を埋める。汚れたままの肌が冷えて、肩が震えた。湿った臭いが室内に充満しているが、換気扇を回すために身を起こすのがこの上なく面倒だった。
界塚には、姉がいると聞いた。名前は、よく覚えていない。軍人だと言っていた。
会えば、何か分かるかもしれない。
しばらくして、扉の下部のハッチから湯とタオル、服が差し込まれた。のろのろと起き上がり、スレインは熱い湯で顔を洗った。
じゃら、と鎖が鳴った。
手錠を繋がれたまま、背に銃口の硬い感触を感じながら、スレインは歩く。久しぶりの通路だ。こんな薄っぺらな靴底でも、音が響き耳を打つ。
かつては、ひと月と空けず踏んだ床。面会室への道のり。記憶より長く感じる。もしかして、自分は緊張しているのかもしれない、とスレインは思った。
馬鹿なことだ。
道の先、扉が開かれる。無理を通せるくらいの月日が流れたのだ。
一年ぶりの面会室で目の前に座る女性に、スレインは目を凝らした。視力をほとんど失っているので、顔立ちが見えないのが残念だった。多分、髪は長い。多分黒髪。平均的な体型のようだ。界塚伊奈帆に似ているかどうかは分からない。目で得る情報より、他の器官の情報量がはるかに多い。日の匂いがするとか、吐く息吸う息が柔らかいとか。硬く跳ねる足音。椅子に座るスカートの衣擦れの音。その場に満ちる張り詰めた空気。スレインは、彼女が向かいに座った瞬間にああ、やはり身内なんだな、と不思議と納得した。
何というか。佇まいというか、在り方があの男と似ている。
「スレイン・トロイヤードです」
相手が息を呑んだのがわかった。
「界塚ユキ准尉。界塚伊奈帆の姉です」
緊張と怒気を帯びているが、柔らかく、綺麗な声だった。優い発声だ。
「界塚伊奈帆は、死にましたか」
空気がキン、と鳴るように凍った。呼吸の音が殊更意識されるが、スレインは待った。界塚伊奈帆の姉が、ぎり、と奥歯を噛み締める音が聞こえた。
「ああ、もう」
苛立ちを隠さない声で、彼女は机を両手で叩いて立ち上がった。スレインは界塚ユキの顔がある方を見上げる。睨みつけているであろうその目を見られないのが、また残念だった。
「貴方、自分が誰に何を聞いているか分かっているの」
「正気です」
「……教えてあげない」
「そうですか」
「……」
「……」
防音が施されたこの面会室では、お互いの存在以外の音はしない。
息を吐く音。息を吸う音。
椅子の動く音。椅子が床を擦る音。
衣擦れの音。
靴が床を叩く音。
テーブルの上の指先の音。
そしてため息。
「僕は、後悔しているんです」
スレインの言葉に、ユキが「何?」と聞き返した。
その言い方が、本当によく似ている。
「界塚伊奈帆には、借りがある。それを返していない」
「借りって……」
スレインは服の上からペンダントを握った。これがこの場所でずっとこの心臓の上にあるのは、きっとあの男のおかげだ。これが何なのか、言ったこともないのに。界塚伊奈帆は、アセイラムがこれを持っていたのを知っていた。もしかしたら、自分のことを彼女から聞いていたのかもしれない。
アセイラムは、地球で鳥を見たと言っていた。界塚伊奈帆と一緒にいた。不思議なことだ。
界塚伊奈帆は、僕を殺そうとは思わなかったのだろうか。僕を殺す機会を棒に振り、あまつさえ、何度も会いに来るなんて。
「僕を生かした。勝手に死ぬなんて許さない」
「貴方ねえ!」
光だけを捉える瞳で、スレインは界塚ユキに顔を向けた。そういえば、界塚伊奈帆が声を荒げたところを見たことがある。月だ。互いの銃の先。彼の目はあの時もノヴォスタリスクでも、左しか見られなかったけれど。
海で、銃を介した静かな瞳が、機械の眼を見た最初で最後。
あいつの目。もっとよく、見ておくんだった。
「ユキ、さん」
界塚伊奈帆の姉の名前を発声する。その時は、少しだけ鼓動が速くなった。ユキ、というのは日本語のsnow。
美しい名前だ。
「お願いがあります」
それから十五分後、スレインは界塚ユキの運転する乗用車の後部座席に座っていた。車のエンジン音が大きいが、さっき鳥の声が聞こえた気がする。潮の香りが鼻孔をついた。ほんの少し、海を視認できないことを残念に思う。
「どうするのよ」
界塚ユキが、ハンドルを荒々しく操作し不貞腐れたように言った。スレインは、窓の外に向けていた顔を運転席に向ける。お互い見えてはいないが、最低限の礼儀に思われた。
「どうしましょう」
貴方ねえ!そう言って、ユキはますますアクセルを踏み込んだ。Gがかかり、体がシートに縫い留められる。カタフラクトに乗っていた感触に似ている。星の海に懐かしさを感じる。もう乗ることはないだろうし、それは無理なことなのだけれど。
――ここから出る。助けてほしい。
スレインはそう言った。呆気に取られるユキの手を引き、面会室のガチャガチャと重い扉を開け、スレインは飛び出した。どこに向かって走ればいいのか分からないが、とにかく足を動かした。途中から、なぜかユキがスレインの手を引いた。ユキに導かれ、走る。二人分の靴の音が、静かな通路に反響した。途中途中、書記官、監視官、事務官、看守たちがいた気がするが、見えなかった。でも、誰も何も言わなかった。追い掛けられもしなかった。
息を切らして走っていくと、突然視野が明るくなった。
空気が変わった。
風が吹いた。とても冷たい。頬にぞわりと鳥肌が立った。でも、不快ではない。
外に出たのだ。
凸凹した砂利道を、二人で走った。立ち止まると、車のドアが開く音。身を滑り込ませる。大きな音を立て二度ドアが閉まった。エンジン音。振動がシートから伝わる。急発進した車は、大きく車体を揺らしてスピードを上げた。
後部座席で、スレインはそっと息を吐く。どうしてこの人が助けてくれるのかをスレインは想像しない。想像しても意味はないし、それをすると息が止まりそうだったから。
会えば、殺されるかもしれないと思っていた。それが一番良いとも思っていた。しかし現実は、界塚ユキはスレインを車の後部座席に乗せ極秘施設から遠ざかっている。脱獄幇助だ。理屈に合わない。論理的ではない。しかし、想像していないが想定されたことだ。
スレインは、聞いた。
「ところで、本当に界塚伊奈帆は死んだんですか」
ユキはきっとバックミラー越しにスレインを睨み(もっとも、それはスレインには視認できなかったが)、飲み込むように言った。
「……そうよ」
「いつ?」
「一年前」
面会が途切れたのもそのくらいだ。葬式をしたと、看守の一人が言っていた。
本当だろうか。
「どこで?」
「それは言えないわ」
しばらく、沈黙が続いた。スピードが落ち、車体の揺れが少なくなった。潮の香りはずっとしている。懐かしい匂いだ。水と、生き物の生と死を凝縮したような生臭い匂い。地球の匂いだ。
前方から、ユキの声が聞こえた。
「お葬式をしたわ」
お墓もあるわ。声は、上擦っていた。スレインは、界塚伊奈帆の葬式と墓を想像しようとしたが、上手くいかない。しかし、ユキの声が示す感情の一端は理解できた。
父親の葬式を思い出す。遠い記憶だ。ふと、界塚伊奈帆には両親がいなかったことを思い出した。母親というのは、スレインにも物心ついたときにはいなかったからよく分からないが、この人は優しいし強い。あと、とても大人だ。きっと、界塚伊奈帆にとっては姉が母のようなものだったのかもしれない。時折見せる声の調子や呼吸に、家族の匂いを感じ取った。
車がまた、がたごと揺れる。車道から逸れたようだ。
「僕には、そんな気はしないんです」
「何よ」
言葉を選ぶなんて、そんなことはしない。優しさなんて感情は、月に置いてきた。後悔なんて感情は、あの地下へ置いてきた。心なんてものは、どこかにやってしまった。スレインは、界塚伊奈帆の姉を脱獄の共犯者にしたことについて、思考と感情を遮断した。意識して、表情を消し去る。
「勘です」
「か、勘?」
高い声で問い返すユキに、スレインは続ける。多分、冷静で腹の立つ声に聞こえているだろう。
それでいい。
「僕を殺せるのはあいつだけ。そして、あいつを殺せるのは僕だけです。僕に黙って、勝手に死んでいるわけがない。絶対にそうはならない」
スレインは、見えない運転席に顔を向けた。ユキが、ミラー越しに視線を送っているのが空気で分かる。口角を上げる。少し引き攣ったが、上手くいった方だ。
「よく当たる。貴方は真実を隠しているのかもしれませんが、分かる。あいつは生きている。なら、僕は会いに行く」
「死んだわ」
即座にそう言ったユキの声は、どこか切羽詰まった響きを持っていた。
「それでも、行く」
黙り込んだユキが、しばらくして大きく息を吐いた。
「……なんだか。貴方、想像と違ったわ」
スレインは座席に背を預けた。手を組んで、握る。
「人は、いろんな側面を持っています。僕は人よりそれが多い」
「そうね。目つきが悪くて不愛想。見るからに冷酷な戦犯に見せかけている。話すと礼儀正しく大人しそうに見えて、無茶で無鉄砲。びっくりするくらい大胆だわ。頑固で、我儘で、もしかしたら、……優しいのかもね。不思議な子」
貴方を慕う人を、何人か知っている。ずっと不思議だったけれど、今日、少し分かったわ。
ユキの言葉を、スレインは二度と想起することはないものとしてただ聞いた。
「でもね、本当になお君はいないの。もう、どこにもいないのよ」
車は悪路を進む。揺れる体の奥で、違う、という声が聞こえた気がした。
肌寒さを感じる。肉体がこのように生々しく環境の変化を訴えるのは久々で、スレインは確かめるように鳥肌を擦った。
ユキに頼んで着いたのは、あの日の海だ。見えないが、音に体を包まれる。風は弱い。波はそれほど大きくはないはずだ。しかし寄せて返す波が紡ぐ音は、耳の奥まで揺らした。
海はもっと、静かなものだと思っていたが。
「ねえ、これからどうするの」
車から降りて、海に向かって立ったままのスレインの数歩後ろ、ユキが聞いた。
「僕は一人で探してみようと思います」
「そんなの無理よ。追われてるのに。それに貴方。…目が、見えないのよ」
あの夜の海は、暗かった。今は明るいらしい。波の音は大きいが穏やかだ。潮の匂いが懐かしさを呼び起こす。
あの時、もっとよく見ておけば良かった。暗い海の色を。星の降る空の色を。向けられた銃口の奥を。自分を映す橙の瞳を。界塚伊奈帆の顔を。
スレインは振り向く。世話になった相手に、せめて普通に笑ってみせようとするが、どうも顔の筋肉が思うように動かない。この笑顔は、全く上手くいかなかった。
「なんとなく、大丈夫な気がするんです。ここでお別れです」
海とは反対方向に歩き出すスレインの手首を、ユキが掴んだ。温かくて、蛸ができた硬い掌だった。軍人の手だ。
手は、あまり似ていない。日本人らしく肌理が細かく滑らかなのも、蛸ができているのも、指先が固いのも一緒だが。
界塚伊奈帆の手は、冷たかった。
「……放っておけないわよ」
遮断したはずの感情が逆流し始めるが、スレインは振り返ることなく立ち止まった。
「放してください」
「捕まったら、死ぬかもしれないわ」
「その方がいい」
「どこへ行くのよ。行き場所なんて、どこにもないじゃない」
確かに。行く当てはない。というか、まずここに来てみたかった。
全てが終わったと思った場所。でもそこは、終わりではなかった。それを確認しに来た。
「行く所も、戻る所も、貴方にはないのよ」
そんな所、これまで一度だってあったことはない。だから、今までと何一つ変わらない。
お人好しに過ぎる界塚伊奈帆の姉に、姿勢を正して向き合う。弟を撃った人間の心配までするなんて、どこまでも姉弟だ。ここで引き留めても、スレインには戻るところはない。それを知っていて、それでも引き留める。その不合理は、彼女だって理解している。
「界塚伊奈帆がいなくなって、…何も言わずにいなくなって、死んだと。そう考えた。でも、どうしてもそんな気がしない」
頭では理解している。それでも、どうしても違う気がした。信じるとか信じないとか、そんな感情論ではなく、あいつはまだこの世界のどこかにいる。確信があった。理由なんて何もない。あえて理由を探すなら、スレインが生きていること。それが理由だ。
「あいつ、どこかにいるんだ。なら、会いに行く」
『また会おう』
界塚伊奈帆はそう言った。
スレインの手首を握るユキの手は、力を失っていた。振り解こうとすれば簡単だったが、スレインは、その手をもう一方の手でそっと外した。
「僕には、この体も心も、失うものは何もない。でも、あいつに言ってやりたい文句の一つくらいはある」
もう、彼女に言うことはない。歩き出したスレインの後ろ、車のドアが開く音と閉じる音がした。そのまま走り去ると思ったが、界塚ユキはスレインをまたしても引き留めた。
「ねえ!」
今度は、正面から回り込み片手を突き出していた。掌がスレインの鼻先に当たる。スレインは言葉を待つ。ユキは息を吸って、吐いて、もう一度吸って、そして言った。
「貴方、なお君…伊奈帆を恨んでいるの?」
「ええ」
簡単なことだ。恨んでいる。
何も言わずにいなくなったこと。
何度も会いに来たこと。
撃たなかったこと。
生きていたこと。
出会ったこと。
全て、棘のように刺さり抜けてくれない。あの橙の瞳。冷静な声。ふとした瞬間の、年相応の仕草。そんなものが自分の命をここまで繋いだ。界塚伊奈帆を探すために、彼の姉まで利用して。
……変われば、変わるものだ。こんなに生き汚くなったのは、あいつのせいだ。
「もしも。もしも生きていたら、どうするの」
何度も閉じる蓋をこじ開けようとする罪悪感を押し込めて、スレインは微笑みを浮かべた。全然可笑しくない。ちっとも嬉しくない。何一つ幸せじゃない。きっと、この笑顔は醜い。
せめて憎んでくれればいい。殺してくれればいい。そんな気持ちでスレインは笑った。
「死んでいるんじゃ、なかったんですか」
「もしもの話よ」
低い声だ。本当に、界塚伊奈帆の身内なんだ。家族なんだ。この人は。
「そうですね」
もしも会えたら。それはあまり考えていなかった。とにかく会いに行かなくては。それだけだった。でも、そうか。もしあいつが生きていたら、会えるかもしれない。
「今度こそ、拳銃で額を打ち抜いてもいいけれど」
目の前の彼女が、息を詰める気配が伝わる。スレインは首を振った。
「それはやめておきます」
会ってから、考える。そう言うと、ユキはどうしていいか戸惑った様子で立ち尽くした。大きな溜息が聞こえ、スレインは胸元に何かを押し付けられた。
「せめて、これくらいは持っていきなさい」
ナイロンのがさがさした手触りだ。探るとファスナーがついている。デイバッグのようだ。
開けると、中には細々したものが入っていた。中には紐のついた靴と、折りたたまれた布が幾つか。服だ。小さなノートのようなものと、クリップで留められた細長い紙の束。あとはごちゃごちゃしていて分からない。
「着替えとパスポート。お金。小切手。あとは携帯食料と日用品が入っているわ。持っていきなさい」
そういえば、今の自分は囚人服を身に着けているのだった。何も考えていなかったことを改めて思い、界塚ユキのこの用意の良さに驚く。
「どうしてですか」
彼女に会ったのは、今日が初めてだ。どうして、こんなものを用意してあるのだろう。
界塚ユキは、全くもう、と言った。呆れたような、しかし優しい声音だ。
「……なお君にね、頼まれたのよ。貴方がどこかへ行きたいと自分から望んだら、私ができる範囲で助けてほしいって」
この荷物、随分前になお君が残していったの。だから、私は貴方を連れて出たのよ。彼女はそう言って、最後に呟いた。
「全く、手のかかる弟だわ」
スレインは、手の中の荷物を握りしめる。あいつは、どういうつもりでこんなことをしたのだろうか。それ以前に、自分の姉になんてことを頼むんだ、と思い、自分が言えた義理ではない、とスレインは自嘲した。
波の音がわんわんと頭蓋で響く。全く、海とはこんなに煩い場所だったろうか。ああ、岩に波がぶつかる。引く潮が砂を攫う。引く波と押す波が共鳴する。
ざあ、ざあ、ざあ、ざあ。
波の音の間に、ユキが「スレインくん」と呼ぶのが聞こえた。がん、と頭を殴られたような衝撃に、足元が少し竦む。そんな風に名前を呼ばれるとは、思ってもみなかった。
「ここから先に、私は行けないわ。仕事もあるしね……。だから、貴方は自分で行くしかない。目は見えない。味方はいない。行く場所も、帰る場所もない。捕まったら、きっと殺される。それでも行くの?」
優しい言葉だった。温かい声だった。少しだけ、ほんの少しだけ、界塚伊奈帆がスレインと話す時の声に似ていたかもしれない。
「ええ。でも、あの施設の人たちは、できるだけ僕のことを隠そうとするでしょう。軍は、僕を捕まえることはできない」
「どうして?」
確かに、すんなり逃がしてくれたし、追ってはこないけれど。ユキに、スレインは自嘲気味に口を歪めた。
「あの人たちは、優しいから」
人間のように抱かれた。手を握られ、頬を包まれ、愛の言葉を告げられた。そっと流された涙に知らぬふりをした。
彼らも、人間だ。その優しさにつけ込んで、心を盗んだ。同情としか理解できぬその情を利用した。そのうち殺されるだろうと、そう思っていた。しかしだれ一人、自分を殺すことなく、追うことすらなく。
そしてきっとこの先、もう会うこともないだろう。
「……そう」
何かを察して、ユキは頷いた。この人も、とても優しい。優しい人間ばかりだ。こんなに汚れきって、生きる価値を失ったがらくたにさえ、これほどまでに優しい。
酷い世界だ。
「ありがとう。界塚伊奈帆のお姉さん」
界塚ユキは、スレインの肩に軽く触れた。ぽんぽん、と軽く叩かれ、驚きで背中が引き攣る。
一度、界塚伊奈帆もこんな風に僕に触れた。
「貴方のことを許しはしないけれど、…行ってらっしゃい」
そんな言葉を言われたのは初めてだ。
スレインは奥歯を噛みしめて、目を固く閉じてそして開く。合っているだろうか。この言葉は。
「行ってきます」
バッグを肩に背負い、歩き出す。足で踏む度、砂が沈んだ。
着替えをして、電車に乗った。
とりあえず、新葦原に向かうことにする。そんな所にいないだろうが、界塚伊奈帆の生まれ育った場所だったはずだ。歩いてみたかった。
新葦原は、人がいた。沢山。若者も多い。楽しそうな話し声や、音楽が聞こえる。店も多く、宣伝が聞こえてきた。匂いがする。食べ物、香水、体臭、植物の匂い。久しぶりに嗅ぐ様々な匂いに、頭がくらくらした。
歩いていると、ラジオかテレビのニュースが聞こえてきた。立ち止まり耳を凝らす。緊急速報や、非常事態宣言や、そんな物騒なニュースは一つもなかった。
僕は死んだはずの人間だ。探すとしてももっと専門性の高い機関が、水面下で動くことになるのだろう。早く捕まえてくれたらいい。行動と矛盾しているが、スレインは人の波を歩き出した。
道中、何人も声を掛けてくれる。どこに行くのか、場所は分かるか、一緒に行こうか、助けがいるか。正体には気付いていないらしく、残念に思う。一人くらい、気付いて殺してくれても良さそうなものだが。
三日ほど、何事もなく過ぎた。次の目的地に向かう。海外にいる可能性もあるだろう。パスポートが入っているとユキに聞いた。見えないから中の写真や名前が分からないが、なんとかなるだろう。空港へ向かうことにする。
旅路に不便は多いが、慣れてきた。それに、道行く人がいろいろと世話を焼いてくれる。火星にいた頃は、こんなこと一度もなかったのに。今になって受ける第三者の善意に気が狂いそうだ。
叫びだしたくなる。
ここにいるぞ。貴方たちの敵は、ここにいるぞ。
スレインは何も言わず歩き続ける。時々、通行人に肩がぶつかり「大丈夫?」と体を支えられた。ありがとう、と言えたが、声が震えた。
全然ありがたくなんてない。
電車やバスを乗り継ぐ。一日で行けるかと思ったが、乗り換えを間違えたり、少しトラブルがあって時間が掛かってしまった。適当に夜を明かして、出発する。日の高い頃、何とか空港の近くのバス停に降りた。
歩いていると、肩を叩かれ、おい、と声を掛けられた。立ち止まると、勢いよく腕を引かれる。力強い、大きな手の平だ。
「本物だ」
若者の声。抵抗する理由もないので、そのまま身を任せる。腕と肩と頭を羽交い絞めにされ、されるがままに足を前に出す。次第、周囲に車の音が多くなる。排気ガスの臭いに鼻が痛む。
キイイィ―――。
タイヤのゴムが路面を削る音がした。おそらくドアの開く音。突き飛ばされ、少し硬い布地で強かに肩を打った。バタンという音。肩の下からエンジンの振動。狭い。車の中だ。ドアが一度開けられ、閉める音と同時に空間が地面と平行移動した。
揺れは少ない。
車に押し込められ、攫われたらしい。戦犯であることがばれたか、単純に、誘拐か。どちらにしても、仕方がない。界塚の顔がちらつくが、すぐ消えた。
「本物なの?」
運転席の方から女性の声がした。こちらもかなり若そうだ。スレインは、口も手も、どこも拘束されていないことに気が付いた。
後部座席は自分一人だけだ。さっきいくら無抵抗だとしても、無警戒に過ぎる。しかし抵抗する気も理由もないので、そのまま横になっていた。突然、疲労感と倦怠感が体中に広がる。深く息を吐く。この後は監禁か拷問か、もしかしたら殺してくれるかもしれない。頭の中の界塚が小言を言ったが、仕方がないだろう、とスレインは見えてもいない目を閉じた。前方の二人は、小さな声で事務的な会話をしている。聞き取れないし、そんな気力もなかった。
死ぬのか。
やっと楽になれる、と思う反面、またしても界塚の顔が浮かぶ。怒った顔で(本人は表情に出ていないと思っているのかもしれないが、バレバレだ)、ぐちぐちと理屈を並べて、生きろ、という意味の小言を数種類のバリエーションで繰り出してくるのだ。
分かった。分かった。でも、ほら、仕方がないだろう。僕は体力もないし、武器もないし、目は見えない。恨みを持った人間に誘拐されて殺されたとしても、それは仕方がないだろう。そんなことを脳内の界塚に話し掛ける。
「伊奈帆の言う通りになった」
耳に飛び込んできた助手席の男の声に、スレインはかっと目を見開いた。血が逆流したかのように頭が熱い。
伊奈帆。界塚伊奈帆。
「界塚伊奈帆はどこに…?」
スレインが身を起こす。しゃべった、と驚いた声を出して助手席の男が動いた。
振り向いたらしいが、顔は見えない。微かな視界で目を凝らす。思ったよりずっと若そうだし、所作は一般人らしい感じがした。スレインはゆっくりとシートに座り直す。両手を膝の上で組んだ。敵意はないことを示したいが、大きな期待はしていない。助手席の男は、顔を逸らさなかった。
「……界塚伊奈帆は、どこにいる?」
抑制した声で、冷たく聞こえるようにそう聞く。男は顔を向けたままシートに肘をついて体を捻った。運転席の女性がちょっと、と制止するが男は構わず名乗った。
「俺は、カーム・クラフトマンっていう」
肌に射抜くような視線を感じる。ぎりぎりと込められた何らかの感情を掴もうとするが、その前にふっと視線が緩んだ。カームと名乗った青年は言う。
「伊奈帆の友だちだよ」
友だち。スレインはよく見ようと目を凝らした。ひどい顰め面に見えているだろうが、関係ない。
カームという男は、なるほど言われれば界塚伊奈帆と同年代に思える。髪や肌の色は薄く、日本人ではなさそうな感じだ。声は溌溂として、若々しい。
そうか、あいつ、友だちがいたんだ。スレインは茫然とした気持ちで目を瞬かせた。
「カーム」
運転席から、咎めるような声が聞こえた。彼女も、そうか。界塚伊奈帆の友だちなのかもしれない。
そうか。
界塚伊奈帆には、日常も居場所もあったんだ。帰る場所も、そこで待っている人も。そういう当たり前のことにようやく思い至った。
「悪ぃ、ライエ。ちょっと話させてくれ」
カームと名乗った男はそのままの姿勢で話し出した。車は速度を変えず、静かに走行を続けている。
「戦争で、俺らは同じ船に乗っていた。俺は整備士で、伊奈帆の機体をメンテしてた」
だとしたら、いい腕をしている。確かあのオレンジ色のカタフラクトは、練習機だとエデルリッゾが言っていた。地球軍のエースパイロットの搭乗するカタフラクトだ。こんな若者が整備しているとは思ってもいなかった。
「スレイン・トロイヤードさんよ」
名を呼ばれ、スレインは首の後ろがぞわりとした。
界塚伊奈帆以外の人間に名前を呼ばれるのは、背中を氷が滑り落ちるような感覚がする。こめかみを、細い汗が伝った。
「お前、伊奈帆のことをどう思ってるわけ?」
静かだった車の走行音が、耳を手で塞ぎたく大きく感じる。体が小刻みに揺らされ、現実感が希薄になる。
空は高く、風が吹く。いろいろな匂い。いろいろな音。人と人とが交わす声。数日間歩いた世界。これが現実のはずだ。数日前までいた、あの暗い場所。名も知らない軍人たちに監視され、監理され、ただ生を消費する日々。
死人同然の囚人にたった一人会いに来る年若い隻眼の将校。
彼には、家族があった。友だちがいた。帰る家があった。そんなことに今更思い至るなんて、と歯を食いしばった。もう、何がなんだかわからなかった。
「俺にとっては同級生で大切な友だちだった。左目の後遺症で、……死んだ」
「後遺症?」
後遺症。左目の。眼帯の下。触れた瞼を思い出す。
『……額を、撃ち抜いたつもりだった』
閉じられた瞼は、触れると一度だけ強張った。彼の顔に触れた記憶が、つい先ほどのことのように指に宿った。
吐き気がした。
「ああ。お前が撃った」
カームは左目を閉じて、人差し指を目の端に当てた。もっとも、スレインには認識できなかったが。
アナリティカルエンジン。スレインの脳裏に、もっとずっと以前、初めて面会した時の伊奈帆の黒い眼帯が浮かんだ。
『もういらないから』
外したと聞いた。
「あれってさ。脳にすごい負荷がかかるらしい。月まで見えた、って話だ」
いつだったか、随分前にマリルシャン卿との決闘のことを聞いてきたのを思い出した。あれは実際に見ていたことだったのか。
肝心なことは、何も言わないやつだ。スレインの握りしめた拳が、みしりと音を立てた。
「脳が損傷して、なんか体がおかしくなっちまったんだと」
一年前。最後に会った日のことを思い出す。そんなこと、何も感じなかった。何も知らなかった。僕は死人のくせに、次が、当たり前のようにあると思っていた。
……いや、今思えば、おかしなことはあった。
あの日はどうしてだか、あいつが本当にそこにいるか不安でしょうがなかった。だから、柄にもなく口をついて出た言葉に、自分でも驚いた。触らせてほしい、だなんて。人間みたいなことを言って。
触れた先の冷たい手。丸みのある柔らかい頬。眼帯の下の閉じられた瞼。側頭部の銃創。
界塚伊奈帆は、そこにいた。生きている人間として。
『僕も、君に触れていいかな』
あいつも、この顔を触った。冷たい指先と、かさついた厚い掌。頬を撫でる感触。額を押す指先。後頭部を包むように掴んだ手。その感触を覚えている。界塚伊奈帆という男は、まるで割れ物を触るように慎重に、手を這わせた。時々、指先を強張らせながら。
自分も、どうかしていた。あいつも、どうかしていた。でも、生きていた。二人とも。
その夜はどういうわけか、眠ることができた。目が覚めると朝になっていたのは、実に数年ぶりのことだった。戦争の間も、戦争の前も、満足に眠りについた記憶はあまりない。
『また会おう』そう言った。その言葉は、声は、いつもと同じだった。
でもあいつは、来なくなった。
「死んだ?」
「ああ」
カームはあっけなく言った。スレインは、頭と心がどうも上手く働いてくれなくなったことに気が付いた。何も考えられないし、何も感じられない。焦点の合わないぼんやりした視界はどこともしれない前方に向いて、見える世界は真っ暗になったようだった。呼吸がしにくい。自分の呼吸音が聞こえた。僕は生きている。界塚伊奈帆は、死んだらしい。背中が熱いような冷たいような、ぞわぞわと気色の悪い感触がした。歯の根が合わず、奥歯が小さな音を立てた。
『でも、君は世界の中で生きている。現実は何も変わっていない』
煩い。煩い。煩い。
カームが大きなため息をついた。スレインははっとして、意識を向ける。視界が少し明るくなった。
「俺はさあ、わっかんないんだよ。どうして、伊奈帆は今でもお前を気に掛けるのか。撃たれて、姫さん連れてって、戦争の首謀者、大罪人だ」
全くだ。自分にだって分からない。スレインは頭の隅っこで考えた。頭の中心は、意識を失わないように呼吸をするよう命じていた。
「俺は整備士だから、現場の空気みたいのは知らない。どうして伊奈帆がお前に入れ込むのか」
カームは苛立ちをぶつけるような声音で捲し立てる。ああ、くそ、という舌打ちが聞こえ、沈黙が降りた。
スレインは口を開いた。
「僕を殺してくれるのか?」
カームが腕を伸ばした。首を掴むだろうと思われた手は胸倉を掴んだ。引き寄せられ、スレインの腰が浮く。
「どうしてそうなる」
至近距離で、朧げに顔立ちが視認できた。金髪で、色白の肌にはそばかすがあった。青みがかった灰色の瞳は、怒りと憤りでぎらついていた。
「それ以外に、何がある? どうして僕は、ここにいる?」
カームはしばらく静止して睨んでいたが、舌打ちをして放り出すように手を放した。シートの背もたれに背がぶつかる。
「頼まれたからさ。伊奈帆に」
カームの呆れた声が頭上から聞こえた。
頼まれた。どういうことだろうか。意味が分からない。界塚伊奈帆は死んだと言っていた。
「遺言だからさ。俺がどう思おうが、関係ない」
カームは体を前に戻しシートに座った。
「あんたを送り届けるのが、目的だ」
それだけ言って、カームは口を閉ざす。
エンジンの音、空調の音、路面をタイヤが削る音が耳の奥で混ざり合う。時間の感覚がないが、長いこと走っているように思う。
どこに向かっているのだろう、とスレインはようやく考える。視覚から得られる情報は何もない。車がときどきカーブに差し掛かり、体が遠心力で傾く。停車することはなかった。信号はないのか、全部青なのか。周囲を他の車が走っているのか分からない。少なくとも、クラクションの音は一度もしなかった。
「目印だって、言ってたんだ」
カームが言う。落ち着いた声だった。スレインは、声に出さずその言葉を口の中で転がした。
目印。
「オレンジ色なんて目立つからさ、塗り直すって言ったんだけどな。あいつ断ったよ。目印みたいなものだから、って言って」
あのカタフラクトのことを言っているのだ。地球でも、宇宙でも、オレンジ色の機体には界塚伊奈帆が乗っていた。タルシスで戦闘した地球の機体では、同じ色の物は無かった。
「最終決戦では、伊奈帆がカスタマイズしてくれって言う通りに整備したよ。接近戦用の武器とシールドを限界まで積んでな」
余計なペイロードだ。機体のバランスを調整するのが大変だった。並みのパイロットなら、宇宙に出た瞬間狙い撃ちだろうな。元は練習機だったんだ。そんなのに乗ってるやつは、伊奈帆以外に知らないし、いない。カームは誇らしげにそう語った。
その後、少し逡巡したような間があり、カームは声を落として言葉を紡いだ。
「今となっては、全部お前を助けるためだったんだな、って思うよ」
スレインは、巻き付いたワイヤーと掴まれた左手を想起した。その意味を、今更のように理解した。カームが、それとな、と世間話をするような声音で続ける。気安い声だった。
いつの間に、この男はこんなに会話の距離を縮めてしまったのだろうか。運転席から、呆れたように鼻を鳴らす音が聞こえた。
「伊奈帆があんたに会うために、俺は何回も運転して連れてってやったんだぜ」
あいつ、左目が見えないから。運転できねえんだ。
それきり、誰も何も言わなかった。
車のドアが開くと、花の香りがした。
「ここだ。降りろよ」
スレインはアイドリングを続ける車から頭を出して地面に足を下ろす。後部座席のドアを閉めると、カームともう一人は車を発進させ走り去った。スレインは深く息を吐き、空気を吸い込んだ。花の香りはこの数日で何回も鼻孔を通り抜けたが、この香りはどこか懐かしい感じがした。
しばらくそうしていると、誰かが傍に現れ肩を支えられた。触れ方が優しい。
「こちらへどうぞ」
知らない声だ。促され、スレインは足を進める。少し行くと、花の香りが溢れる、風が踊る場所に足を踏み入れる。日の光が頬に温かい。足元には草が生えているのか、柔らかい踏み心地だった。
花の香りが馨しい場所を通り過ぎ、少し暗い、涼しい空間に移る。
室内のようだ。ジェントルな仕草で椅子を進められ、クッションの膨らんだ、座り心地の良い椅子に座らされる。拘束もなく、一人そこへ据え置かれた。訳も分からずじっとしていると、すぐ近くに食器の音。
「紅茶です」
先ほどと同じ声だ。…自分には、似つかわしくない言葉だ。足音が遠ざかる。そのままじっとしていると、扉の開く音の後、軽い足音が近づいてきた。
「スレイン様」
驚いた。そちらへ顔を向けるが、よく見えない。分かるのは黒っぽい影。影は跳ねるように近づき足音が靴裏から伝わった。
「その声は。……エデルリッゾさん?」
目の前に、ふわりと風が起こった。手を取られ、握られる。記憶にあるより長い指。ほっそりとした手が震えている。掌は柔らかく、ほのかに温かい。
「ああ、スレイン様! 生きておられたのですね」
彼女は跪いているようで、スレインは声を頼りに見下ろした。大人びた声になったが、変わらない素直な響きでスレインは微笑む。結構ちゃんと、笑えた気がする。
「お久しぶりです」
「はい。スレイン様、また、お会いすることができるなんて」
ひっく、としゃくり上げる声が聞こえた。涙を拭ってあげたいが、そんな資格はない。スレインは握られた手を握り返した。
「……どうして、地球に?」
スレインが聞くと、はい、と鼻声が聞こえた。
「私は、戦争が終わってから地球にいます。姫様との約束で」
「アセイラム姫との……?ああ。もう、姫ではありませんね」
「ああ、つい。スレイン様とお会いしたら、昔に戻ってしまったようで」
最後に会ってから、もう三年だ。月にいた頃のことを、違う世界のように思い返す。
エデルリッゾと共に過ごした時間。いつ目覚めるとも知れないアセイラムの生命維持装置の前で、二人で祈りを捧げた終わりのないような日々。その思い出は四肢を、意識を、正気を引き裂かれるように痛みを伴うが、あの時エデルリッゾの存在は自身の孤独を慰め、希望を繋いでくれていた。
今となっては、彼女が健やかに成長していることに、喜びを感じる。こんな感情を抱く資格など、ないのは分かっているのだが。
「エデルリッゾさん。お元気でしたか」
スレインは、微笑みを浮かべる努力をした。口の端がぴくぴくと痙攣して、今度は上手くいかなかった。エデルリッゾが握る手に力がこもる。短い爪が手の甲に少し食い込んだ。
「はい!スレイン様。またこうして名前を呼んでいただける日が来るとは思いませんでした」
涙声は明るく朗らかだ。スレインは、彼女の名前をもう一度呼んだ。もう、呼ぶことなどないと思っていた。
「僕もです。お顔がよく見えないのが、残念です。美しくなられたでしょうね」
確か、十六歳になっているはずだ。ふと、アセイラムと二人で見た地球の姿が瞼の裏を通り過ぎた。
あの時は、そう。姫様はまだ十五歳だった。それほどの月日が流れたのだ。まだ何も知らない、幸せな幼い二人をそっと胸の奥に仕舞う。次に取り出す当てなど、ないのだけれど。
もう、戻らないのだ。
エデルリッゾは、恥ずかしいです、ともごもごと続けた。
「私は、地球のことを、姫様に……アセイラム様にお伝えしています。その、もう侍女ではありません。アセイラム様の友人として」
アセイラムが今どうしているのか。スレインはこの数日、街中のニュースや人々の雑談からしか知らない。お健やからしい、ということを知り、ほっとしていた。
「……そうですか」
エデルリッゾは、アセイラムの傍を離れた。クルーテオの居城で、いつも一緒にいた二人を思い出す。本当の姉妹のようにも見えた。そこでスレインは、月で別れたもう一人の姫は、今頃どうしているだろうか、と考える。考えること自体、罪だとは分かっているが。
できれば、自分の事など忘れ、幸せに暮らしていてほしい。叶うなら、地球にいてくれたらいい。海や鳥や、雲や花。美しいものをあの空色の瞳に映し、優しい風に包まれ、桃色の髪を揺らし、日の光を浴びてあどけなく微笑む。夢のような想像をした。
「地球での暮らしは大変なこともありましたが、今ではすっかり慣れました。スレイン様に教えていただいたことを…いえ、あの」
息を詰まらせて黙り込んだエデルリッゾは、手をもじもじさせた。くすぐったい。
「どうしました?」
「すみません。私、もう一つの約束を果たすため、スレイン様をお待ちしていたのです」
「約束?」
「界塚伊奈帆さんとの」
その名に、スレインは見えない目を見開いた。
そういえば、おかしなことが多すぎた。界塚ユキ、友人と名乗る二人組、そしてエデルリッゾ。
用意が良すぎる。
そうか。界塚め。
収容所を出たら、僕が迷わずここへ来られるよう準備をしていたのか。
『その気になれば、こんなところ出て行けるんじゃないのか』
悔しいが、全部あいつの思い通りになった。スレインはエデルリッゾに聞いた。
「界塚伊奈帆は、死んだのですか?」
室内から音が消えた。エデルリッゾが、手を離し立ち上がった。ソファがぽす、と跳ね、スレインの隣に彼女は座った。
「お会いしたのは一年くらい前です。その後、人づてに、お亡くなりになったと聞きました」
スレインは膝の上の手を組んで考える。死んだ、死んだと、みんなが言う。
でも、違う。もはや確信だった。しかし、界塚伊奈帆が何のために、こんな回りくどいことをしたのか理解できない。
それも、会えば分かる。
「約束って?」
「私のお預かりした約束は、これです」
何かが掌に乗った。両手で形状を確認する。
「……鍵?」
金属でできた薄い、小さな鍵だ。
「どこの鍵で、何の鍵かは知りません。ただ、スレイン様に会ったらこれを渡してくれと。あと、伝言を」
「伝言?」
エデルリッゾは、こほんと咳払いをして息を吸った。はっきりとした声が鼓膜に響く。
「『オレンジ色からコウモリへ』」
「……ああ」
「それだけです」
「……分かりました。ありがとう」
エデルリッゾが、ほっと息をついた。彼女は元気よく、跳ねるように立ち上がる。年頃のレディなのだから、もう少しお淑やかに、といらぬ心配をしてしまう。
「空港まで、お送りします。運転は任せてください」
エデルリッゾの元気な声に自然な笑みが浮かんで、スレインは首を振った。
「せっかくですが、飛行機には乗りません。できれば、駅にお願いします」
一年前。
「久しぶりです。エデルリッゾさん」
「界塚伊奈帆さん。お久しぶりです」
こうして直接会うのは一年半ぶりだ。彼女は背が伸びて、立ち居振る舞いが大人っぽくなった。
時は確実に流れている。
伊奈帆が訪れたのは、地球火星間の友好を目的として建造された迎賓館だ。火星出身者なら、条件を満たせば一時的に滞在することができる。
その庭を、伊奈帆とエデルリッゾは連れ立って歩いていた。豊かな木々と花々が溢れ、水が湧き、風が通る。
地球らしさを象徴するような庭だった。
「地球には、慣れましたか」
エデルリッゾに歩調を合わせて、伊奈帆は尋ねた。二人の背丈はそれほど変わらないが、歩幅は違う。落ち着いた、優雅な身のこなしだ。
「おかげさまで。いろんな所を転々としましたから、大変なこともありましたけど」
鳥の羽ばたきが聞こえ、エデルリッゾがそちらを見上げた。飛び去った後だが、彼女は足を止め、空の先をしばらく見つめていた。
彼女も、あいつから鳥の話を聞いたことがあるのかもしれない。
「地球に住むんですか」
「はい。もしかしたら、いつかは火星へ帰るかもしれませんが。地球は、もう一度来てみたかった。まだまだ、知りたいことが沢山あります」
エデルリッゾは伊奈帆の横に早足で並び、微笑んだ。道なりに庭園を進む。
「でも、そろそろ定住しようかと思っています。所在がはっきりしている方が、何かと便利なので。住むなら、新葦原がいいと、ずっと思っていました」
最初の場所ですから。
その言葉に、セラムに背負い投げをされたことを思い出す。今思えば、あの頃は誰もが子どもだった。
「そうですか」
「はい」
アセイラムの侍女だったエデルリッゾは、今でも深い親交があるのだろう。女王の口添えがあれば、この建物の職員として、ここに住むことはできるだろうな、と伊奈帆は判断した。
薔薇園に足を踏み入れた。
赤い薔薇が咲いていた。とても良い香りがする。赤と、黄色。そして白。
綺麗ですね、とエデルリッゾが言った。伊奈帆は綺麗だとは思ったが、返事をせずに立ち止まる。先を行ったエデルリッゾが振り向いた。
「スレイン・トロイヤードは生きている」
「……え?」
向かい合う二人の間を、そよ風が通り抜けた。薔薇の葉が、さわさわ揺れる。遠くで、呼び鈴の音。近くに噴水があるのか、風に乗って水音が流れてきた。鳥の羽ばたきが、また聞こえた気がした。この庭には、鳥が住んでいるのかもしれない。
優しい音に彩られた沈黙の中で、エデルリッゾは、菫色の瞳を丸く見開き伊奈帆の顔を凝視している。彼女の後ろ、揺れる若葉の合間から見える空がとても青い。ここはやはり、地球の庭だ。
「そんな」
エデルリッゾは、口元を両手で覆った。目はこれ以上ないほど見開かれたままだが、徐々に潤んで瞬きの合間に睫毛が濡れた。雫が頬を伝った。幾筋もの水滴が伝い落ち、薄く赤らんだ頬が濡れそぼっていく様子を、伊奈帆は何も言わずに見ていた。
「本当なのですか?」
ひっくり返った声で、エデルリッゾはようやくそう言った。伊奈帆の隻眼は、涙に濡れた菫色の瞳をじっと見据える。
「貴方が信じれば」
エデルリッゾは固く目を閉じ、両手を組んで神様、と小さく呟いた。伊奈帆は、神様なんていない、と思った。しかし彼女がそう言いたい気持ちは、よく分かる。
「びっくりしました。こんなことって……。ええ、でも、信じます」
エデルリッゾは頬を濡らす涙を両手で拭って、微笑んだ。伊奈帆は微笑み返す。
「あの方が、生きておられたなんて……」
涙を流して、彼の生存を喜ぶ人間がいる。それがこんなにも心を慰めるなんて、と自身の心の動きに伊奈帆は驚いた。いつの間に、こんなにあの男に入れ込んでいたのだろう。
「伊奈帆さん。ありがとうございます」
ぴょこん、と跳ねるようにお辞儀をして、エデルリッゾは言った。大人びた彼女の、久しぶりに見る幼い仕草に伊奈帆の口元は綻ぶ。彼女は両手を胸の前で組み、伊奈帆を正面からてらいなく見つめた。真っ直ぐな眼差しだった。それを逸らさず見ることができる自分を、伊奈帆は喜ばしく思った。
「スレイン様を救ってくださったのですね。あの時の姫様との約束を、果たしてくださったのですね」
エデルリッゾは、アセイラムと一緒にいた。そこで約束をしたのは、もう一人の伊奈帆だ。伊奈帆の自我はそれを後から知った。だから正確には、約束を交わしたわけではないのかもしれない。その記憶は、もう取り出した。形も何もない。記憶にもない。それでも、その願いを今の自分は知っている。
あの時、アセイラムの願いを受け取った。スレインにその願いを伝えた。いつしかその願いは、自分の願いになった。今、自分の一部となった。
彼の未来を願うようになった。
「救った、ということについてはどうでしょうか」
伊奈帆の独白のような呟きに、エデルリッゾは不安げな顔で口を噤んだ。
エデルリッゾは、温かい人だ。そして、スレインのことを大切に思ってくれている。伊奈帆は、スレインの理解者に、ようやく自身の思いを語ることができる。気が晴れる心地だった。
「スレインは、死ぬことを望んでいた。……いや、今でも。一発の銃弾で彼の願いは叶ったかもしれない」
エデルリッゾが両手で口元を覆い、痛ましい顔をした。彼女は、自分の知らない月での彼を知っている。彼の願いも、苦悩も、喜びも、アセイラムへの思いも、ずっと見ていた。もしかしたら、最もスレインに近しい人間かもしれない。彼が死にたがっていたのを、彼女は理解できる。
「でも、僕は死ぬことが救いと考えるほど、ロマンティストではありません。戦後彼は地下でずっと、強制された生を味わっている。死ぬことを選ばないが、生きることを放棄して。僕にできることなんて、何もない。時々会いに行くことだけ。歯痒くて、悔しくて、イライラする。スレインは、その気になればどこへだって行けるはずだ。それをしないのは、セラムさんと、顔も知らない、死なせた、傷つけたと思い込んでいる沢山の人々と、多分、僕の為だ」
鳥の影が頭上を横切った。伊奈帆は言葉を失い立ちすくむエデルリッゾに一歩、二歩と近づく。
「いつか、未来を生きてほしいと思っている」
笑顔は昔から苦手だ。あいつと出会ってから、また下手になった。でも、昔よりずっと素直に笑えるようになったと思う。
「貴方に、お願いがあります」
「お願い?」
伊奈帆は右手を差し出した。エデルリッゾが、掬いあげるように両手を合わせ近づける。その両手に、ころんと伊奈帆は触れずに渡した。
「もしもスレインと会うことがあれば、これを渡してほしいんです。それと、伝言を」
それは鍵だ。味も素っ気もない、ありふれた真鍮のシリンダーキー。古びて、光沢を失っている。
「どうして…ご自分でお渡しにならないのですか?」
界塚伊奈帆は笑った。少年のような、老人のような。悔しそうな、諦めと希望を浮かべた顔だった。エデルリッゾは、こんな風に笑う人をもう一人知っている。
「僕が死ぬから」
ちょっと早すぎた。だから、力を貸してほしい。界塚伊奈帆は言った。
風が通る。
朝のひやりと清涼な空気を吸い込むと、胸の辺りがさわさわする。静かな、深海のような空気だ。閉じた瞼の中、細い糸のような血管の流れる色が見える。日の出だ。こうして世界は地上に浮かび上がる。
伊奈帆は、朝が好きだ。世界が起き出す瞬間を、独り占めしたような気分になる。
開け放たれた窓から入り込む空気が、薄汚れた黄色いカーテンを揺らした。海風が、ベッドの掛け布に影で遊ぶ。
あと何度、このように朝を迎えることができるだろうか。
何度も転んで、その度に方向を見失いそうになる。泥だらけの膝や尻をはたいて、スレインは歩みを進めた。顔や首に木の枝が擦れひりひりする。血が出たようだ。手の甲で拭い、歩き続ける。
空気が冷たくなってきた。暗いし、夜が近いのかもしれない。今日中に着くことは無理か、とスレインは野宿について頭を巡らした。
目的地は、一つしかない。スレインは、フェリーを降りて日が昇る前からその場所への道のりを歩き続けていた。大きな国号に沿って歩くが、所々崩れて戦争の爪痕を残している。山に飲み込まれたひび割れた道を、必死に進んでいた。
まだ目がよく見えた頃、空から見た地形を思い出す。小さな島に見えたが、それは高い場所にいたからだったな、と当たり前のことを実感していた。あの時の戦闘で、この島の地形も変わった。そしてもうずっと前、ヘヴンズフォールの時、この島の地形は大きく変わっていたのだ。空から、それも見えた。
こんな所で待っているなんて、悪趣味なやつだ。
もういない火星の父の顔が浮かぶが、すぐに消した。
生きるほど、心を殺すのが上手くなった。地球の父のことも、母のことも、その思い出も、機械的に閉じることができる。今では、アセイラムのことさえも。
しかしあいつだけは、どうもいけない。どんなに掻き消そうとしても、追いやることができない。図々しく脳裏に居座り、あれこれと指図する。食事はしたか、眠れたか。傷の具合はどうだ。今日は晴れた。全く、煩くて仕方がない。
オレンジ色め。この呼び方を思い出してから、早く来いと喧しい。
完全に光源がなくなり、夜の冷気が汗ばんだ肌を冷やしていく。すっかり日が落ちたことを体感し、それでもスレインは歩き続けた。どうせ見えないのだ。暗くても関係ない。今は時間が惜しい。味のしない携帯食を齧り、どこかの水道で汲んだ錆びた味のする水を口にしつつ、血豆だらけの足を踏み出す。
界塚伊奈帆のいる場所へ。
種子島の、地球連合軍基地の隠しドッグへ。
それからまた、随分歩いた。
足の裏が気持ち悪いが、どうでもいい。夜通し歩き、日が昇るころ、朽ち果てたドッグに辿り着いた。
人気のない施設の中を歩く。土の匂いと、オイルの匂い。鉄の臭いが埃が混ざり合っていて、少し噎せる。奥に進むため錆びた手すりを辿る。掌を擦り剥いて血が出た。
何度か階段を登っていくと、空気の不純物が少なくなってきた。床や壁が平らになり、スニーカーが硬質な足音を叩き出す。探りながら歩くと、等間隔でドアが並んでいるのが分かった。宿舎だろうか。端から虱潰しに、ドアを開いて呼び掛ける。中は埃っぽく、咳き込み止まらなくなった。鍵は掛かっておらず、簡単に開いた。
エデルリッゾから渡された鍵を使うことになるのだろうか。次々扉を開けるが、鍵の掛かった部屋は、まだない。
何度か通路を曲がり、階段を上り下りして、声を限りに名前を呼ぶ。区画が変わる。機械的にドアを開けていく。部屋の中の強い臭いに、鼻が痛む。消毒液の臭いがするようになった。
こんなところに、本当にいるのか。不安が胸を掠めるが、どうせ他にすることもない。徹底的に探してやろう、と次の扉に手を伸ばす。
ドアノブを回して押す。
開かない。
「……ここに、いるのか」
触った感じは、他の扉と変わらない。ドアノブの真ん中に、丸い出っ張りがあった。指で触ると、その中心に鍵穴がある。握りしめていた鍵を差し込む。予感がした。
『また会おう』
鍵と鍵穴がぴたりと合い、回すとカチャリと音がした。
開く。
風が通る。
薬品の臭いと人の匂いが、微かにした。
「……界塚、伊奈帆?」
「……やあ」
名前を呼ぶと、数メートル先から呑気な声が聞こえてきた。スレインは、声の在り処へ近づく。途中、何かにぶつかってガタガタと音がした。手で確かめると簡素な椅子のようだ。脇にどけて、ベッドらしい白い塊の傍へ寄る。
呼吸の音が聞こえる。見下ろす白の中にぽっかり黒いのは髪の色だろう。呼吸の合間に、そいつは嬉しそうに小さく息を漏らした。
界塚伊奈帆の声だ。
「ぼろぼろだね」
言われて、何度も転んだことを思い出した。服が、泥か血で湿っている。急にずきずきと、体中が痛み出した。
「ここに来たっていうことは、君にはもう全部分かっているんだろうな」
落ち着いた理性的な声だ。かつて聞いた声と変わらなく思う。スレインは、足を棒のように真っ直ぐ立って界塚の声の方に顔を向け頷いた。
「ああ」
空気が丸くなった。界塚が笑ったのかもしれない。
「全部、芝居だったんだろう」
「……ばれたか」
その声は、いたずらを見つかった小さい子どものように無邪気だった。
死んだふり。死んだふり。死んだふり。そう、死んだふり。誰のための? 何のための?
「自分の葬式までして、色んな人を巻き込んで。やることが派手だな」
変則的な生前葬をしたのだ。軍関係者に対しては死んだと周知し、親しい人たちには別れの挨拶をする。界塚ユキに会った時から、スレインはずっとその可能性を考えていた。
『でもね、本当になお君はいないの。もう、どこにもいないのよ』
『全く、手のかかる弟だわ』
「いいじゃないか。そのおかげで、君はこうして来てくれた。十分だ」
くすぐったそうに笑う界塚は楽しげだ。しかし呼吸の合間にヒュ、と苦しそうな響きが混ざっていることに、スレインは苦々しい表情を隠せなかった。
「カームという人に会った。もう一人いたが、名前は分からなかった」
「親友と戦友だ。元気そうだった?」
「ああ」
スレインは、界塚は喋るのも辛そうだとは思ったが、話を途切れさせるつもりはなかった。この男が存外話好きで、寂しがりだと知っている。
「エデルリッゾさんとは、どうして?」
「君と初めて面会してからすぐ、彼女に連絡を取って会った。それからも定期的にメールでやり取りを。その縁で親しい」
界塚が咳き込んだ。ふう、と大きな息を吐いた。
「当時は、君のことを知りたくて。色々聞いて回っていたんだ。月でのことを聞いた。彼女の主観だけれど。それを聞いていたから、僕は君を優しい人間だと思ったんだ」
初めて界塚が面会に訪れた日のことを思い出す。チェス盤を広げて、感情の読み取れない顔でそこに座り、言葉を交わした。アセイラムをセラムと呼び、彼女の願いを語った。気が付くといなくなっていて、それから数か月後、雨の日に現れた界塚はやけに挑発的に絡んできたことを思い返す。
それから数え切れないほど繰り返された面会で、無表情で軍神の二つ名を持つこの男が、それだけの男ではないと知った。
チェスが強くて。
料理が好きで。
話が長くて。
お節介。
意地っ張りだが存外素直で。
いつだって、僕に伝えようと。一つの目でじっと見て。手を机の上で握り締めて。口を開き。
何度だって言うんだ。彼の思いを。彼の願いを。
未来への。
「このかくれんぼの目的は、僕を生かすためか?」
「それもある」
「お姉さんのため?」
「それもある」
窓がある。風が踊り、土や血で汚れた僕の髪がばさばさ揺れた。ガア、ガア、と鳥の声が聞こえ、遠ざかった。波の音がずっと聞こえている。潮の香り。光は柔らかい。スレインは、横たわる界塚の体を背にして、ベッドに腰かけた。
「分からないな」
「そうかな」
一番の理由はね、とほくそ笑み、界塚伊奈帆は深くベッドに沈み込んだ。スプリングが軋んで音を立てる。首を回し、界塚へ顔を向けた。少し顎を引く。よく見えないが、笑ったような気がした。
「君に、僕を探して欲しかった」
スレインは、施設を飛び出してここに至るまでの道程を辿る。界塚のことを探していたが、本当に見つかるかは分からなかった。誰もが言うように、もう死んでいるのかもしれないとも思った。それでも、界塚を探した。彼の一片のようなもの。住んでいた町。そこでの日常。歩いたかもしれない道。行くかもしれない場所。そんなものを探した。
「僕は以前、ずっと君を探していたんだから」
そうか、とスレインは思った。
探していたのか。
僕のことを。
界塚伊奈帆は、本当に馬鹿だ。
「お姉さんが、泣いていた」
界塚ユキの声。綺麗な声だった。優しくて、温かい。怒っていたし、戸惑っていた。僕を憎んでいたはずだった。それなのに、行ってらっしゃい、と送り出してくれた。声は震えていて、その後嗚咽が続いたのを耳が拾った。
「……しょうがない」
寂しそうに界塚は呟く。きっとこの男は、姉に自分の死を見せたくなかったのだろう。また、それ以上に自分がやりきれなかったのだろうと考えた。
「お前、病気か」
「うん」
この部屋の扉を開けてから、病気の臭いがずっとしている。もう長くないことは直感的に分かった。
「死ぬのか」
「まあね」
いつも通りの声で界塚は答えた。スレインは自分の両手を組んで握る。呼吸が苦しい。腹がぞっと冷えて裏返る感覚があった。言葉が出てこない。
お前が生きろと言ったのに。
「……スレイン」
その声に顔を上げ体を向けると、手を握られた。界塚の手は、汗で濡れて冷えていた。冷たい。ああそうだ。これが界塚の手だ。手を上向きに開かれ、何か硬い物が置かれた。界塚は両手でスレインの掌ごとそれを握り込む。
「それ、あげるよ」
界塚の手が離れ、スレインは手をゆっくり開いた。両手で手の中の物を転がす。丸くて、つるりとしている。一か所、細いコードのようなものが密集していた。指で、形を慎重に何度もなぞる。
「これは?」
「形見かな」
界塚が言って、スレインはそれが何か理解した。
「趣味が悪い」
「ははは。君のせいで、それをつける羽目になった」
苦虫を百回噛み潰したより最低の気持ちになったスレインを見て、界塚は明るく笑った。笑顔があるだろう場所を睨みつけると、界塚はくくく、と更に笑いを漏らした。
「……病気は、僕が撃ったせいか」
「まあね」
その声に、何の憎しみも恨みも悲しみも含まれていないことを、全てを受け入れて正しく自我を認識していることを、スレインは恨みがましく思った。できることなら、詰って恨んで、百万回だって殺してくれたなら。
言いたいことは、あったはずだ。恨み言はこっちだって山ほどあるはずだった。でも、こうして実際に界塚に会ったら、それらは霧のように消えてしまった。
忍び笑いが聞こえる。今日の界塚は、よく笑う。
「しかし、君がここまで来るとはなあ」
「馬鹿にするな」
「その目、どれくらい見えるの」
スレインは、界塚に顔を近づける。呼吸が触れ合うくらい近づきようやく、彼の橙の瞳を認識できた。
ああ、この目だ。遠い日、あのチャンパーで見た色。月で見た色。海で見た色。薄暗い地下で見た色。ぼやけているが、何とか見える。
この目を追いかけて、ここまできたのだ。
なぜだか、右目が熱くなって開けていられなくなる。界塚の指が頬に触れた。拭うような動きに、スレインは自分が泣いていると気が付いた。冷たい両手で顔を包み込まれ、額が触れた。
「もう最後だ。僕を撃ってみる?」
冗談めかして言うが、本気だ。そのためだ。界塚伊奈帆がスレインを呼んだことは。
「それとも、僕が君を撃とうか」
今なら、撃ってあげてもいい。優しく、穏やかな声だった。愛の秘密を交わすような。
触れ合った額が熱い。界塚の額から、汗が伝った。呼吸が浅く速い。スレインは頬を包んだ手を外し、顔を遠ざける。見下ろすように体を起こして、界塚の手を握った。がさがさして、弾力がなくて、汗で濡れていて。これがあの界塚の手かと思うと、見えない瞳から次々涙が溢れてくる。
「……それもいいと、思ったんだが」
自分の声はみっともなく裏返ったが、うん、と界塚は次の言葉を待っていた。スレインは、首を振る。
「随分前に、それはやめた」
「じゃあ、何しに来たの。こんな廃墟に、たった一人で」
それはもう。言いたいことが、あったはずだった。でも今では言葉にならなくて。自分の鼓動に耳を澄ます。緩やかで大きな鼓動だ。深く息を吸う。どういうわけか、指が震え出した。界塚の手を手で確かめる。彼はくすぐったそうに身じろぐ。別れたあの日に触れたように、手から腕を辿る。薄い布越しの腕を、掴む。
これがお前か。お前の腕か。どういうわけだ。軍人が、こんなに痩せてしまって。
筋肉が落ちて骨と皮だけになった腕を辿り、骨の出っ張った肩から鎖骨を触る。汗で濡れていて、汗疹があった。首も筋張って、大きな血管がぷくりと浮かんでいる。そこを押すと、どっ、どっ、と速い血流が伝わった。
尖った顎に触れ、丸みを失った頬を包む。頬骨のあたりに、湿疹。顔は熱い。瞼に触れ、額に触れ、髪に触れる。ごわごわした髪を、何度か梳いた。そして側頭部に残る古い銃創を人差し指で撫でる。
僕の手を、界塚の手が覆った。
このままでいてほしい、そういう意思表示に思えた。
窓から差し込む光がカーテンで揺れる。
風が温められ、優しく通り過ぎて行った。海の音は小さく穏やかだ。
ずっと、そうしていた。海が凪ぎ、視界が狭まり、空気が少しずつ夕焼けの香りを運びはじめるまで。
もう、そこまできていた。
「……お前、死ぬのか」
「……そろそろ」
左手の指で界塚の唇に触ると、ひび割れて薄皮が剥けていた。少し濡れている。屈んで舐めると、血の味がした。触れ合った唇が、微笑みを形作るのが分かった。息を交換するように近い場所。スレインは途方に暮れて聞いた。
「僕は、これからどうしたらいい?」
界塚は鼻を鳴らした。もう一度、唇をくっつけてくる。微かに触れ合わせながら、界塚が言葉を紡いだ。
「知らないよ。好きにしたら。そのつもりで、いなくなったんだから」
彼を探すために、スレインはあの場所から出た。
いつ捕まってもいいと思っていた。いつ死んでもいいと思っていた。でも、そのいつかは来なかった。泥だらけ、土だらけ、傷だらけになってやっと着いたこの場所は、目指していた場所だけれど最果てではないことを知った。
「……界塚」
「スレイン」
よく来たね。そう言って、界塚はスレインの両耳を引っ張った。合わさった唇の間で、窒息しそうになるくらい深く舌が交わされる。
まだ生きている。まだ生きている。まだ。もう少し。もう少しだけ、一緒にいてくれ。
そんな声が聞こえてくるようだった。橙の瞳が、その光が、命の灯が、はっきり見えた気がした。
「僕は、もう君を生かすことも殺すことも強要しない。自分のことは自分で決めてくれ」
「僕は……」
界塚はどさりとベッドに沈んだ。ぜえぜえと呼吸が乱れ、何度か咳き込んだ。背をさすることができず、胸をさすった。肋が浮いていて、汗で服が張り付いていた。呼吸が整い、ありがとう、と小さく礼が聞こえた。
「……最後に、一つだけお願いがあるんだけど」
「何だ」
「名前を、呼んでほしい」
「名前……?」
「伊奈帆って。聞こえなくなっても、ずっと呼んでほしい」
吹きこむ風が冷たくなってきた。布団を肩まで掛け直してやる。スレインは腰の位置をずらして、胸の近くへ屈み、彼の顔を覗き込んだ。髪を撫でる。目を閉じたようで、橙色が見えなくなった。
「……伊奈帆」
「うん」
吐息のような返答。途端、喉が痞える。ごくりと唾を飲みこんで、もう一度名前を呼ぶ。
「伊奈帆」
「うん」
「伊奈帆」
「……スレイン」
聞こえないほど微かな声だが、名前を呼ばれた。スレインは、伊奈帆の口元に耳を近づける。
「……何?」
「元気でね」
堪え切れなくて、背を丸め蹲る。いけない。名前を呼ばなくては。痙攣する喉をこじ開け発声する。変な声が出た。
「………伊奈帆」
「……」
伊奈帆は何も言わない。スレインは、もう一度髪を撫でた。耳に触れた。頬に触れた。温かい。
「伊奈帆」
聞こえているだろうか。口を大きく開けるが、なかなか上手く声を乗せられない。大きく息を吸った。
「伊奈帆」
肌寒い。風が強くなってきた。夜の匂いがする。波が何度も岩肌にぶつかるのが、遠く聞こえる。
「伊奈帆」
手が震える。喉も。寒気でぶるり、と背が震えた。
触れているところは、もう冷たい。
「伊奈帆」
冷たい頬に頬を寄せた。耳に口を近づける。
聞こえるか。聞こえるか。聞こえているか。
「……伊奈帆」
動かない頭を抱え込む。鉛のように重く感じる。腕に強く力を入れると、首が変に撓った。がくり、と落ちそうになる頭を胸に抱く。
「………伊奈帆」
ああ、最初から、こうしていれば良かった。今頃気付くなんて間抜けすぎて、どうしようもない。スレインは固く目を閉じた。
「……………伊奈帆」
生きているうちに、抱きしめてやれれば良かった。体だけでもぴったりとくっついて、寂しくないようにしてあげれば良かった。
「…………………伊奈帆」
真っ暗だ。何も見えない。風の音がする。海の音がする。星の落ちる音がするようだ。
「………………………い、なほ」
界塚伊奈帆はいなくなってしまった。もう、ここにはいない。どこにもいない。
「……………………………馬鹿な、やつ」
元気でね、なんて。どうしろっていうんだ。
お前はもういないのに。
夜の闇が圧し掛かり、風が突き抜け海がぶつかり星が飛ぶ。
遠い夜明けが訪れるまで、スレインはずっと名前を呼んだ。
スレインは、伊奈帆の亡骸を海で燃やした。煙に目や鼻が沁みて、涙や鼻水が止まらなくなった。眩暈がして、砂浜に尻もちを着く。ごほごほ噎せた。何度も煙を吸い込み、噎せた。時々吐いた。胃液以外は何も出なくて、その臭いにまた目が沁みた。
ずっと、そうしていた。
「……口煩いやつ」
煙が消え、匂いが変わるころ、スレインはぽつりと言った。
食事をしろ、寝ろ、本を読め。………元気でいろ。
「お前は、遺言ばかり残したな」
伊奈帆に手渡された形見を取り出す。丸くて、つるつるして、硬い。一か所から、糸のようなものが数本飛び出す彼のかつての左目。
これを着けたら、もう一度世界を見ることができるだろうか。当てもない想像をして、スレインは膝を支え立ち上がる。全身で風を受けた。潮風が、頬に痛い。きっと目前には、オレンジ色の空が広がっている。
『来るぞ、コウモリ』
あの日と同じ海。同じ空。
あの時は、こんな未来は想像できなかったな。
お前が先に死ぬなんて。それでも僕が、生きているなんて。
瞼の裏の夕焼け色に、もう少し生きてみようか、とスレインは答えた。



コメント