▽花吐き病【嘔吐中枢花被性疾患】△
- μ
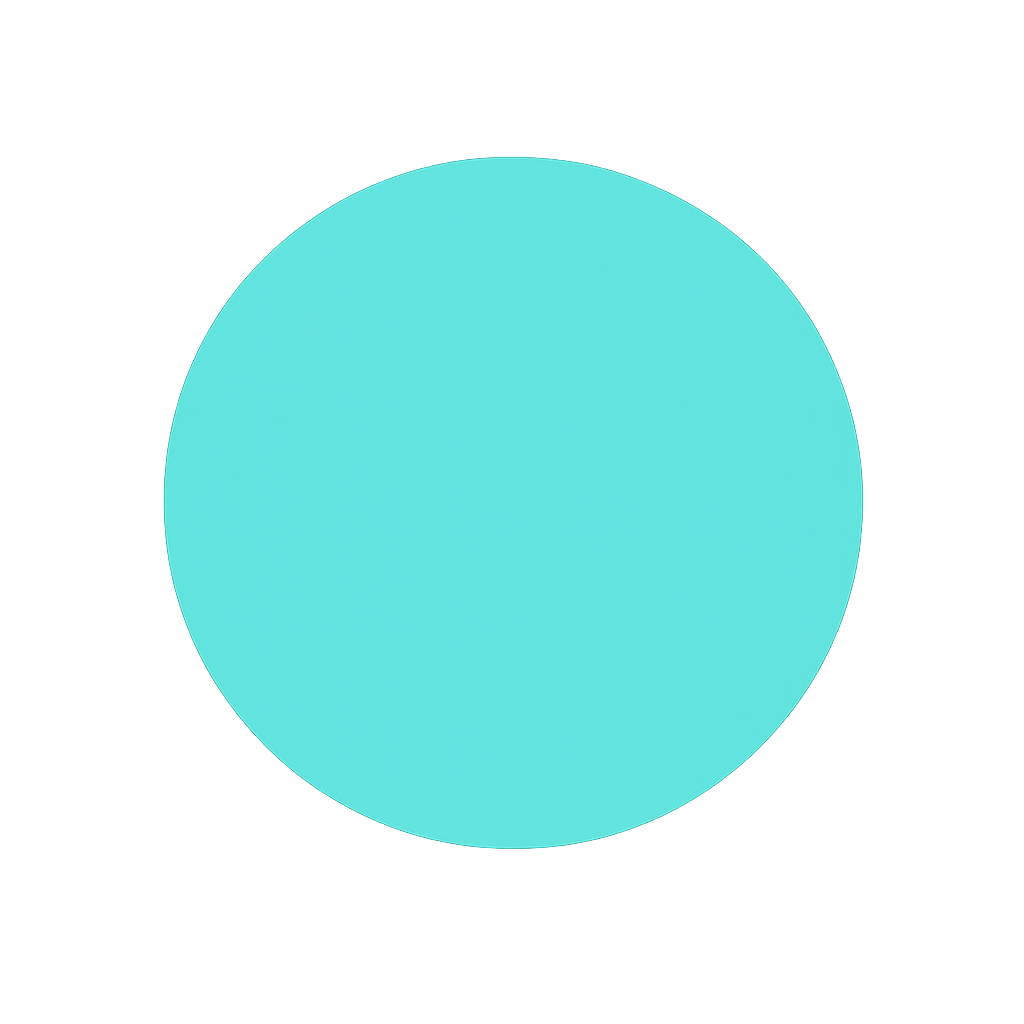
- 5月19日
- 読了時間: 17分
更新日:6月15日
「青い花びら?」
蝉の声が洪水のように押し寄せる真夏日。極秘施設での面会を終えた伊奈帆が外に出ると、熱い風が通り抜けた。伊奈帆のから青い欠片が風で飛ばされ、しばらく宙返りを繰り返した後地面に落ち、張り付いた。伊奈帆は不思議そうに呟く。
「花びらなんて、いつ、ついたんだろう」
「少し痩せたね」
いつもの面会室で、伊奈帆は開口一番そう言った。スレインはむっとして、にらみつけるように伊奈帆を見る。実際は少しではなく、かなり痩せて見える。元々肉付きの良い方ではない彼は、この一月で頬骨が目立ち、目の占める表面積が増えたように見える。大きな碧の目の下には、濃い隈ができていた。
「どうしたの。自殺願望?ハンストじゃ死ねないよ」
「…そんなつもりじゃない」
「隈もできてる。眠れないの」
「…君は、僕の何だ」
問い詰める伊奈帆にいらいらと言い返すスレインの顔は青白かった。唇が乾いてひび割れている。
「…そうだな。…味方、になりたいと思っている」
「…そう、か」
「辛そうだ。休むかい」
伊奈帆の言葉で立ち上がったスレインは、よろけてテーブルに手をついた。指まで青白い血管がはっきり浮かんでいる。伊奈帆はその指の形を凝視して、眉を顰める。
ふらつく足でスレインは、面会室から独房への道のりを歩き出した。
薄暗い独房。冷たい床には、無造作に散らばる青い花びら。
体調の悪いスレインが気になって、伊奈帆は許可を取った上で、独房を訪れた。嘔吐く声がして手早く独房の扉を開け駆け込む。中ではスレインが一人蹲っていた。
噎せ返るような、花の香りがする。
「これは?」
足元の花びらを拾う。中には、散る前の原型を留めているものもたくさんあった。
床一面の、青い薔薇。
「誰かが花を?」
これだけ買うとなると、かなりの金額だろう、と関係のないことが口から出そうになった。スレインは肩で息をしながら、伊奈帆を振り返る。苦しさからか、目元が滲んでいたし汗が額を濡らしていた。
「…違う」
スレインは体を折り曲げ、胸を押さえて喘ぐ。伊奈帆は大きく上下する骨ばった背中をさすった。
「大丈夫?苦しそうだ」
背骨が浮き出た背中の肉は肋骨の数もわかるくらいだった。汗で濡れた囚人服の下の肌は熱い。
「あ…触るな。…うっ」
ごほごほと噎せ、背中が大きく痙攣する。止まらない咳は、このまま死んでしまうのではないか、と思うほどだ。そして、スレインの口から次々に青い花びらが吐き出された。
「…これは、どうして?花を食べた?」
目を丸くする伊奈帆に、荒い息の合間でスレインが返答した。
「そんなわけ、ない」
「どうして、花を吐くの」
「わからない」
スレインが吐き出した花は、床一面の色を青く塗り替えていた。青い薔薇の香りの中、スレインの背を伊奈帆は撫で続けた。
「最近、顔色が悪くて心配していた。痩せたようだし。このせいか」
落ち着いたスレインを独房のベッドに寝かせ、伊奈帆もベッドの端に腰かけた。青い薔薇はもったいないが、ダストボックスに捨てた。背中越しに、咳払いする声が聞こえる。
「いつから?」
「…三か月くらい前」
「そんなに…なんで言わなかった?」
振り返って見下ろすと、ばつが悪そうなスレインの顔が目に入った。彼は左右に目を泳がせた後、おずおずと口を開いた。
「…その時は、花びらが一枚口の中に入っていただけだった。変だとは思ったけど、それから何もなかったから、何かの拍子に口に入ったんだろうと思った」
「…監獄で、花なんて口に入るわけない」
首を振る伊奈帆の言葉に、スレインが力なく笑った。
「…それから何日か経って、独房で急にせき込んだんだ。その時は、せり上がってくる感じで少し吐いた。花びらが三枚、口から出てきた。」
天井を見て話すスレインの上に屈みこんで目を合わせる。スレインは瞬きをして目を伏せた。
「変だ、変だと思ったが、特に体の調子が悪いわけでもないし、放っておいた」
少し間をおいて、その後、スレインは言った。
「…この一月、よく吐くようになった」
「今日は、何回吐いたの。あの一回じゃないよね」
「八回…だったかな。」
睨みつけた伊奈帆に、スレインは申し訳なさそうに笑った。
「気味が悪いから、できるだけ君に会いたくなかった」
どうして、いつも憎まれ口しか叩かないのに、こんな時は何も言わないのだろうか。
「馬鹿だな」
本当はこんなこと言いたいわけではないのに、と思いながら伊奈帆はベッドに深く腰掛けた。
「最近、また食事を取らなくなったと聞いた。そのせいだね」
そっと、胸骨の浮き出た胸に手を乗せる。びくりと体が強張った。心臓の鼓動が、規則正しく手のひらに伝わる。
「軍医に診てもらおう。申請する」
「すまない」
こんなに素直で殊勝だと、調子が狂う。伊奈帆は言葉を探す。
「…気づかなかった、僕も悪い」
スレインが眉を下げて微笑んだ。ゆるゆると首を振り、金の髪が枕に広がった。
「君は何も悪くない。迷惑をかける」
伊奈帆は立ち上がり、ドアノブに手をかけた。が、振り向いて、スレインを見た。目が合う。碧の目が丸くなる。
「…ねえ、僕は。君を大事にしたいんだよ。わかってくれるかな」
「…」
伊奈帆は戸惑った視線を背中に感じながら、独房を後にした。
「嘔吐中枢花被性疾患」
耶賀頼蒼真が病名を告げた。
「いわゆる、花吐き病だね」
「そんな病気があるんですか」
そう言って、椅子を回転させる。極秘施設内の診察室のパイプ椅子から腰を少し浮かせて、伊奈帆は耶賀頼に聞いた。スレインは、診察が終わると面会室へ連れて行かれた。
うん、と柔らかく返答し、耶賀頼は数枚の写真を示す。そこには、色とりどりの花々と、患者らしい、多様な国籍の少年少女の写真があった。写真の日付を見ると、歴史と言っていいほど昔のものもある。
「昔から、潜伏と流行を繰り返してきた病気だ。 片思いを拗らせると口から花を吐き出すようになる。それ以外の症状は確認されていない。どうして花が吐き出されるのか、そのメカニズムも不明だ。 吐き出された花に接触すると感染する。 根本的な治療法は未だ見つかっていない」
治療法がない。顔を曇らせる伊奈帆に耶賀頼は付け加えた。
「ただし、両思いになると白銀の百合を吐き出して完治する」
「両想い…」
白銀の百合なんて、メルヘンチックでロマンチックな話だが、実際の光景はグロテスクだ。物を吐き出すという行為は、自己防衛の手段だ。体力を消耗し、精神的にも追い詰められる。この写真の患者たちは、完治したのだろうか。それとも。
「患者の様子は良くないね。体力も落ちてる。今の状態が続くと、命に関わるよ」
カウンセリングをしようか、と言う耶賀頼に、申請しますと返答し、伊奈帆は彼の待つ面会室へ向かった。
「君の診察結果だけれど」
面会室のテーブルをはさんでいつものように向かい合う。伊奈帆は、座ると同時に口を開いた。
「嘔吐中枢花被性疾患、というそうだ」
スレインは、じっと伊奈帆を見ている。頭の中で、病名を反芻しているようだ。
「通称花吐き病。片思いをこじらせると、花を吐くようになるらしい」
「はあ?」
「恋の病だそうだ」
「…」
スレインは間抜けな声を出した後、伊奈帆の言葉に顔を真っ赤にさせて俯いた。
伊奈帆はテーブルの上に指を組んで、肘に体重を預ける。これしかない、という心当たりは、口に出すのも馬鹿らしいが、話を進めなければいけない。
「セラムさん?」
「…」
スレインは唇を噛みしめて黙ったままだ。伊奈帆は、どうして自分は知っていたことにこんなにも面白くない思いをしているのだろうと驚く。きっと、いわゆる恋敵、というやつだったからだろうと自分の感情を分析する。
「彼女、夫がいるしな」
「そんな大それたこと、思っていない」
きっ、と目を吊り上げて、スレインが言った。やつれた輪郭の中で、碧の瞳がやけに大きく映る。
「でも、このままだと君が死んでしまうよ」
「花を吐いたくらいで、死なない」
いい加減腹が立ってきた。
「そのせいで食事を取らなくなって、寝られなくなったら死ぬ。この1か月でどれだけ体重が落ちてるか知ってる?」
伊奈帆に対して、少しは申し訳ないと思っているのか、スレインはぐっと言葉を詰まらせて顔を伏せた。
「…食事はする」
「眠れないんでしょ」
「…夢を見なければ、平気だ」
「…僕はいやだよ。花に埋もれて死んでいる君を見つけるのは」
花を抱いて眠る。言葉にすると綺麗かもしれないけれど、人が吐いたり、生きたり、死んだりするのは決して綺麗なばかりではない。あのごつごつした、大きく上下する汗ばんだ背中。汗と胃液と薔薇の噎せ返るような香り。ぐったりと力が抜ける生白い体。生々しくて、ちっともきれいじゃない。
「次に来るまで、ちゃんと生きててよ」
生きようとしている彼は、きれいだと思う。
「叶わぬ恋、か」
家に帰って、夕飯の支度を終えた伊奈帆は、ソファに寝転んで天井を見上げた。
「そんなに人を好きになるものかな」
自分も、セラムに対して好意を持っていないと言えば噓になる。間違いなく、陳腐な言葉で言うと恋をしていた。愛していた、と言ってもいい。アナリティカルエンジンに、自己と同一視しているとまで分析され、勝手に告白までされたのは伊奈帆にとって大いなる痛手だ。しかし、自分は花を吐いたことなど一度もない。
「青い薔薇か」
ふと思い立ち、タブレットを手に取る。検索ページを開き、単語をいくつか入力した。
「遺伝子組み換え技術によって誕生した。人工的に生み出された物ゆえに、当初花言葉は、『不可能・有り得ない』であったが、開発が進みブルー・ローズの誕生を実現させた事から、『奇跡』『神の祝福』という花言葉が新たに充てられた」
不可能だと思っているのか。それでも、奇跡を願うのか。
「どっちだ。全く、矛盾だらけのやつだな」
カチャリと鍵の回る音がして、姉の明るい声が聞こえた。
「…えっ」
数日後の朝、なんとなく胸がむかむかして、洗面所でうがいをすると、口の中から白とオレンジの鮮やかな色彩が飛び出した。
「…まいったな…」
鏡には、普段は不愛想で自分の、困り切った顔が映った。
「これは?まさか…」
面会室のテーブルに置かれた透明なビニール袋の中身を見て、スレインが口を開いた。
「僕も吐いた。まいった」
透明な袋の中には、白色とオレンジ色の花びらが数枚、茎から先の形をはっきりと残すアネモネの花が二輪入っていた。
「…」
気の毒そうな表情で花を見つめるスレインに、伊奈帆は背もたれに体重を預けて言った。
「君、よく正気でいられるよね」
「大丈夫か」
スレインは心配そうに尋ねた。なんだかんだ言って、スレインも伊奈帆のことを気にかけているのだと分かり、伊奈帆は言いたいことを言うことにした。
「…恋の病か。花を吐くというかなり強引な方法で自覚を迫ってくる。吐いた花を見ることで、より一層相手への思いを自覚し袋小路に陥りまた吐く。身をもって体験して分かった。これはきつい」
「…こんな時でも、冷静だな」
スレインが今度は呆れたように息を吐いた。
「問題は、前途多難だということだ」
「前途多難?」
「両想いにならないと治らない。しかし、その見込みがなければ、どうしたらいい」
重苦しい空気が二人を包む。これはいわゆる恋バナというやつかもしれない、と能天気なことが頭の端に浮かぶが、当事者には生きるか死ぬかの一大事だ、と伊奈帆は続ける。
「これまで罹患した人々が、全て両想いになったとは考えにくい。おそらく、心変わりがあり、次第に症状がなくなっていったんじゃないか」
スレインが半分くらいは聞き流している表情で伊奈帆を見る。お前のことなんだからもっと真剣に聞け、と怒鳴りたくなる。
「しかしそれには、時間か出来事が必要だ。このままだと、業務に支障が出てしょうがない。君の命も危ないし」
「僕のことは、別に」
伊奈帆はスレインを睨みつけた。スレインは居心地悪そうに目を逸らす。
「そこで、今日は君に相談がある」
「僕に?相談?」
身を乗り出した伊奈帆に仰け反って、スレインは背もたれに背をぶつけた。
「確かめさせてほしい」
「…何を?」
「僕と君は、誰のことが、好きなのか」
誰も言葉を発しなくなった面会室で、ビニール袋が光を反射してちらちら光る。水に活けないと、このまま枯れてしまうな、とスレインは思った。自分で吐いた花はゴミだと思うが、このアネモネが枯れてしまうのはもったいないな。そこでまで考え、自分に心の中で舌打ちをした。
「不毛な会話だ」
「いや、切実だ。できるなら、今日話をつけたい」
そんな分かりきったことをどうして今さら、顔を突き合わせて大真面目に話し合わなくてはいけないのか。
「…君が言っただろう。姫様には、クランカインが」
「違う」
意外な返答だった。不思議に思い、スレインが首を傾げる。
「何が違う?」
そこで伊奈帆は珍しく口ごもり、しばらくテーブルの上に視線を落とした後言った。
「僕が好きなのは…」
その、一つしかない橙の瞳がまっすぐスレインに向けられた。澄んだ目で見つめられて、スレインはぐっと唾を飲み込む。伊奈帆が静かに唇を開いた。
「僕は、君が好きなのかもしれない」
「………はあ?」
スレインの口は、母音のaの形に開かれたまま固まった。碧の瞳がまじまじと伊奈帆の橙の瞳を見つめ返す。
「…傷つくから、その顔やめてくれる」
唇を尖らせて伊奈帆が言った。スレインは天井を見上げ、目を閉じた。
「…君は、アセイラム姫を好きなんだ」
「いや、確かにそうだが、そうじゃないみたいだ。アナリティカルエンジンのお墨付きだが、だとしたら、とっくの昔に花を吐き出している。それに…」
そこで伊奈帆が目を逸らした。言い難そうにぼそぼそと呟く。
「…君が、夢の中にまで出てくるものだから。…夢見が悪くてしょうがない」
起き抜けに吐くのは嫌な気分だ、と続ける伊奈帆の顔は、彼の姉に「照れてるのね」と評されるだろう。しかしスレインは、大丈夫か、という顔で伊奈帆を怪訝に見つめている。
「…」
「だから、その顔は傷つくって言っている」
「…しかし、どうして君が僕なんかを…その、…」
俯いて口をもごもごと動かすスレインの両手は、手錠の鎖をカチャカチャと落ち着きなく玩んでいる。
「好きになるかって?わからない?」
「わからない」
そこで伊奈帆は少し笑った。スレインは驚いて目を丸くする。伊奈帆が笑うのは、それも声を立てて笑うのは初めてのことだった。今日は、驚かされてばかりだ。
「実をいうと、僕にもさっぱりわからない」
「はあ?なんだそれ」
「いつ会いに来ても、君は暗いし悲観的だし、僕に対して排他的すぎるきらいがある。挨拶しても返事が返ってこないこちらの気持ちを考えたことがあるのかな?たまに喋ったかと思えば、話は抽象的で分かり辛いし。君と付き合うのは本当に骨が折れる」
「ひどい言われようだが、その通りだな」
一息に捲し立てる伊奈帆に、スレインは苦笑いした。そんな相手に付き合うなんて、本当に物好きというか、変な奴だ。
「でも」
伊奈帆が一度言葉を止めて、息を吸った。スレインは伊奈帆のその瞼が閉じられ、そして開かれるのを見た。
「楽しいとも思う」
面会室の壁には、蛍光灯の無神経な光に照らされたいくつかの染みがあった。こんなの気付かなかったな、とスレインは関係ないことを考えながら、伊奈帆の姿を目に映していた。
「君の言葉は分かり難いけれど、君の言わんとすることは明らかで…とても綺麗だ。僕は、君がいるってことを確かめたくて、ここに来るんだ」
伊奈帆は目を閉じて微笑んだ。スレインには、その笑顔がこれまで抱いていた印象に比べあまりに幼く見えて、背中がざわついた。目の前の少年を、じっと目に映す。その碧の双眸を、たった一つの橙色が掴んだ。
「これは、きっと恋なんだと思う」
スレインは、伊奈帆の隻眼から視線をテーブルの上に移した。白と、オレンジ色のアネモネ。伊奈帆らしい色だと思った。
「僕は、君が好きなんだと思う。君は、誰が好きなの」
「それは…」
「今日は、答えてくれるまで、帰らないから」
強情な伊奈帆はきっと有言実行するだろう。スレインは、できる限り素直に、言葉を選び口から出そうと頭を巡らす。
「…僕は、誰かを好きになる資格なんてないよ」
「それ、僕に対してめちゃくちゃ失礼だと思わない?僕は今、覚悟を決めて君に告白したと思うんだけどな」
衣擦れの音までも聞こえる緊張が、面会室に満ちる。蛍光灯のかすかな電気音も聞こえるように静かだ。
「…君が」
スレインが、普段なら聞き取れないほどの声を出した。伊奈帆はそのままの姿勢で、じっとスレインを見つめる。スレインは、俯いて自分の手のひらを見ながら話し出した。手錠がシャリ、と大きな音を立てた。
「君が…、来ない日は。よく花を吐く。それは…君がもう、来ないかもしれないと思うと、言い忘れたことがたくさんある気がして、苦しくて。言葉の代わりに花が喉からせり上がってきて…」
スレインは、指を軽く曲げたり伸ばしたりしながら、掠れた声で言葉をつなげる。
「君が来たと分かると、花のことなんか忘れる。この部屋にいる時は、いつも言い忘れたことを思い出そうとするんだけど、…言いたくもないことしか出てこないんだ」
スレインはそこで、唇を嚙んだ。伊奈帆は黙って割れた唇を見た。
「…君が、帰ると。あの独房に戻ると、花を吐く。突然、取り返しのつかないことした気がして、ドアを見る。そこを開けても君はいないのに、手を伸ばす。苦しくて苦しくて、花が口から溢れてくる」
いつかの、青い薔薇の中に横たわる彼を思い出す。まるで花葬のような光景に、肌が粟立ち毛が逆立ったのを覚えている。
死んでいるかと思った。
触れた背中が熱くて、涙が滲んだことをスレインは知らないだろうな。
「気を失うまで花を吐き出した後、思うんだ」
低く柔らかい響きの声は、少し震えていた。
「君が、…好きだって」
伊奈帆はテーブルに手をついて立ち上がろうと腰を上げ、結局椅子に座り直した。
自分の靴の爪先を見る。土がついていた。最近磨いていない。ここに来る時は、いつも気が急いてそんなことまで頭が回らないんだ。伊奈帆は口を横いっぱいに引っ張った顔が収まってから、顔を上げた。
「…ありがとう」
「…それだけだ」
視線がかち合い、お互いどぎまぎしてそっぽを向いた。伊奈帆はくすりと笑い、スレインはそれを横目で見た。
「…照れるね」
「…」
「今、僕たちは両想いになった気がするんだけど」
「…そうなのかな」
「…完治したら、銀の百合を吐き出すらしいよ」
「ふうん」
「…」
「…」
「出ないね」
「そうだな」
「ねえ、キスしようか」
「は?」
「いや、せっかくだし。もしかしたらそれで治るかも」
がたがたと椅子を揺らして立ち上がる伊奈帆にスレインは仰け反った。
「嫌だ」
「なんで」
伊奈帆はいつの間にかテーブルを回って来ていた。スレインの座る椅子の背もたれに真正面から両手をがっしりとかけた。
「忘れてくれ。そんなつもりじゃない」
精一杯顔を背けるが、何もかもがやけに近い息が肌にかかる。すぐそこに、橙の瞳があるのが分かる。
「じゃあどんなつもり。僕の気持ちを弄ばないでくれる。勇気を出して告白したのに」
「待て、待て待て待て、詰め寄るな、腕を掴むな、顔を近づけるな」
「顔が赤いよ」
「う…」
スレインの茹蛸のような耳をからかい半分に指の背で撫でてから、伊奈帆は真剣な顔で聞いた。
「ねえ…本当に嫌?」
そうだったら、すぐやめるけど。
「うう…」
スレインは、肘を曲げて胸の前で握りしめられていた両手で顔を覆った。手の下にある口から、くぐもった声が漏れた。
「…いや、じゃ、ない。」
けど、怖い。その声は泣いているように聞こえて、伊奈帆は優しい声で聞いた。
「なんで怖いの」
スレインは、顔を覆ったまま微動だにしない。手の平越しに、唇が震えているのが分かる。骨ばった手首。手錠が、痩せて肉の落ちた前腕の中ほどまで下がっている。華奢な腕も震えていた。
「君を、汚してしまうような気がして。…もう、君を傷つけたくない」
伊奈帆は額をスレインの額にこつん、と当てた。鼻にかかる息があたたかい。
「馬鹿だなあ。君は」
「ばっ…!うっ…が、あ…」
伊奈帆の言葉に勢い良く顔を上げたスレインは咳き込み、青い花びらが赤い唇から次々に零れ落ちた。苦しそうに歪められた小さな頬を両手で包む。
「好きだよ。スレイン」
「か、かい…、づか…ん…」
青い花は、苦かった。
ごくりと飲み込んで、深く深く口付ける。
「んん…、ふ…う…」
スレインの手が、伊奈帆の肩を掴んで手錠がカシャカシャと音を立てた。体重のかけられた椅子が不規則に揺れる。そしてしばらくして、二人は弾かれたように離れて大きく咳をしながら体を折った。
「う…ごほ、ごほっ…が…、はあ…」
「があ…、あ…あ…かは、あ…」
数枚の青い花びらに彩られた灰色の床の上、白銀の百合が二輪、床に落ちた。
「青い薔薇の花言葉は、不可能と、奇跡」
次の面会で、出し抜けにスレインが言った。彼から話し出すのはとても珍しいので、伊奈帆は静かに彼の話を聞くことにする。自分から話すスレインの言葉は澱みなく、優しい響きを持っていた。
いつも、困らせたり、怒らせてばかりいてはいけないな。伊奈帆はそっと微笑む。
「アネモネの花言葉は、恋の苦しみ」
「確かに、死ぬほど苦しかった」
伊奈帆の相槌に、スレインも小さく笑った。穏やかな声が、その花について語り出す。
「アネモネは、色で花言葉が違う。白いアネモネの花言葉は、真実、希望」
伊奈帆は自分が吐き出した花の姿を脳裏に描く。あの時はちゃんと見ていなかったから、今度、花屋で聞いてみようか、と思った。
スレインは続きを話す前に、少し間をおき、顎を引いて伊奈帆を見た。
「そして、オレンジ色のアネモネには、花言葉がない」
花言葉がない、と言われたオレンジ色のアネモネ。目立つ色のその花は、意外にも万人の知るところの意味を持ち合わせていないのだった。
「そうなんだ。君、詳しいね」
「別に…」
感心する伊奈帆の言葉にそっぽを向いて、スレインが憎まれ口をたたく。それには、以前のような険悪さはない。
「そうか。ねえ、どんな花言葉がつくだろうね」
伊奈帆が聞くと、スレインは目を細めて笑った。初めて見る穏やかな笑顔に、伊奈帆は目を大きく開いて眦の上がった瞼の中にある碧色を見つめた。
「君のような花だな。伊奈帆」
伊奈帆は、それがスレインなりの愛の告白だと気付いて、頭の後ろをがりがりと搔いた。スレインは、伊奈帆の赤い耳を見て照れたように笑った。



コメント