▽from rain△
- μ
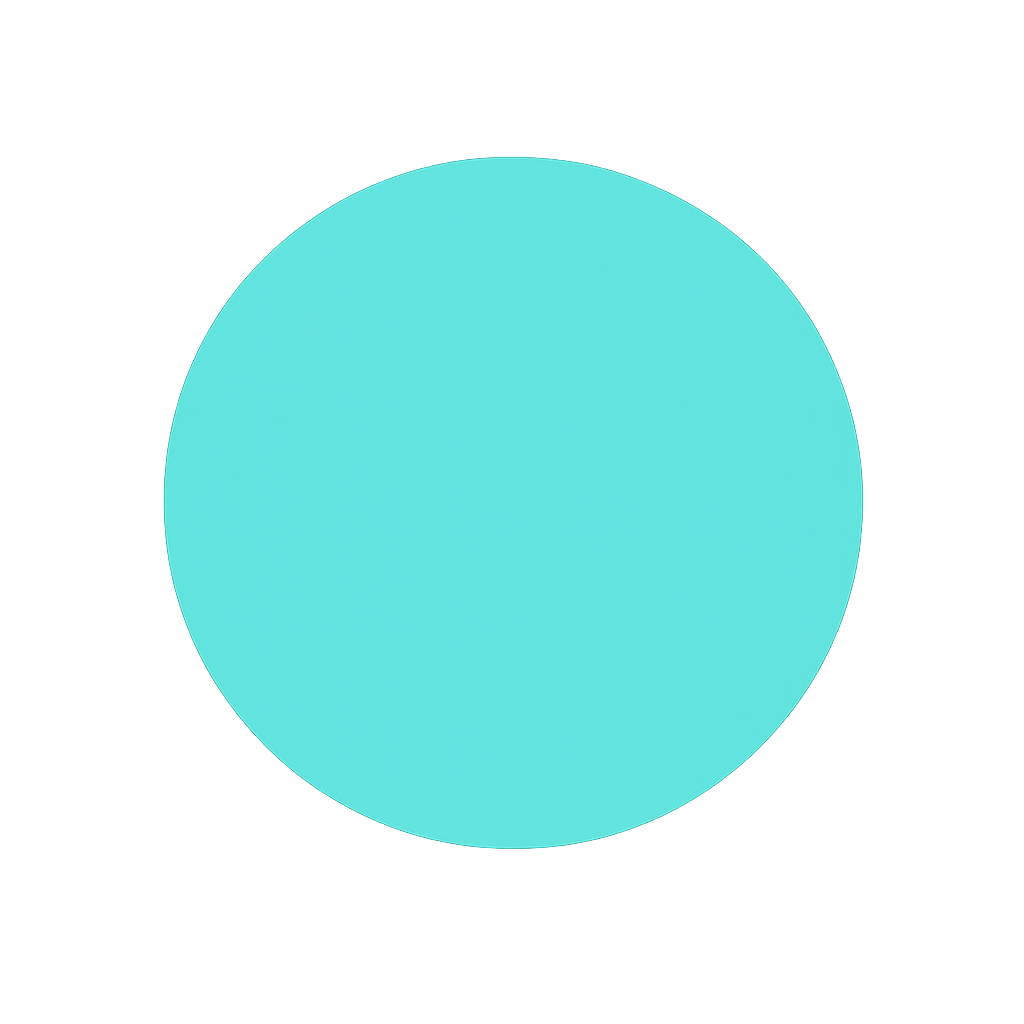
- 6月10日
- 読了時間: 19分
更新日:6月15日
病名はない。
歩みを止め、伊奈帆は空を見る。電線で多角形に切り取られた茜色の空を、雁がV字の隊列で飛んでいる。薄い雲は、紫色のグラデーションに染まっていた。
よく晴れた夕焼け空だ、と伊奈帆は思い、鞄を持ち直し、帰路を再び歩き出す。
あの戦争から八年。僕はサイバネティクス研究所に勤め続けている。自宅は軍所有のマンション。3LDKの住まいは七階にある。所謂社宅というやつで、築年数の割には広くて綺麗で設備もまあまあ。
エレベーターのボタンを押す。扉が開く。乗り込み、数字を押す手がふと止まる。一瞬の躊躇いの後、伊奈帆は七のボタンを押した。
浮遊感。ドアの上の階数表示をじっと見る。
同居人のことを考える。
今頃、夕食を作ってくれているだろうか。冷蔵庫の食材を想起し、メニューの候補が脳内にいくつか上がる。
ポーン、と軽やかな音がして、エレベーターは上昇を止めた。多分、カレーかシチューか肉じゃがだ、と伊奈帆は思い、通路を歩く。
730号室。
玄関のドアを開く前に、こちらに駆け寄る気配がする。なので、僕はドアノブを持ったまま、笑顔に見える目と口元を作る。
ガチャリ、とノブを回してラッチの引っ込む音がする。
「ただいま」
先を制して帰宅を告げる。上り框で出迎えたのはスレイン。エプロン姿で、腕まくりをしている。伊奈帆を認め、頬が綻び笑窪ができた。
「おかえりなさい、伊奈帆さん」
彼の笑顔に笑顔で応える。引き攣らないよう慎重に。
一度振り向き玄関に鍵をする伊奈帆の背中に、スレインの声が優しくかかる。
「カレーと、肉じゃが。どっちが良かったですか?」
その問いかけに和み、伊奈帆はくすりと声を漏らす。"こっち"のスレインは、これを聞くのが好きなのだ。向き直り、靴を脱いで通路に上がる。出汁と醤油がほんのり香る。
「カレーかな?」
伊奈帆は、わざと間違える。スレインはころころと可笑しそうに笑う。
「今日は、肉じゃがです」
「へえ、すごい」
これは本当。肉じゃがどころか、以前は目玉焼きも焦がしてたのに。
「糸蒟蒻も入ってる?」
「もちろん」
「嬉しいな」
リビングに入り、伊奈帆はふとキッチンを見る。コンロに鍋がかけてあって、炊飯器から蒸気が勢いよく吹き出している。
家庭の匂いだ。ボリュームを絞ったテレビのニュースは天気予報を映している。明日の降水確率は90パーセント。
明日は雨か、とほっとする。その顔を彼に見られないよう、僕は窓の方を向く。カーテンは閉まっていて、不自然な動きになってしまったが仕方がない。
言えないことがある。そして、そのことを彼に知られたくはない。少なくとも、僕の言葉や態度からは。
「いただきます」
「いただきます」
ほんの少しずれたタイミングで、食事の挨拶をする。肉じゃがに箸を入れると、柔らかくほぐれ、中から、ほわりと湯気が出る。
「ほくほくしてて、美味しい」
「ありがとうございます」
スレインが箸を使う仕草は自然だ、と。僕は毎日感心する。
「醤油取って」
「はい」
言い終わる前に差し出される赤いキャップの醤油さし。
「お茶いる?」
「あ、もらいます」
テーブルを滑ってきた湯呑みにお茶を注ぎ、彼の手元にコトンと置く。
他愛もない話をしているうちに器の中は空になり、僕らは箸をほとんど同じタイミングで置く。
「ごちそうさまです」
「ごちそうさま。美味しかったね」
ふふっ、と眉尻を下げてスレインは笑う。
彼の作った夕ご飯は美味しくて。
僕を見る目は柔らかくて。
伊奈帆さん、と。
僕を呼ぶ声はどこか甘い。
そんな、ありふれた日常の一コマが、どうしようもなくやりきれない。
幸せなのかもしれない。
けれど。
同じ部屋で眠る夜。決まって夜中に目を覚ます。静かな夜更け。高層階には地上の光も届かない。
聞こえるのは、寝息だけ。
見えるのは、どこかあどけない寝顔。僕は眠るスレインの髪を撫でる。細い猫毛は、指の間をさらさら通る。清潔で健康な髪に触れ、安らかな寝顔を眺めていると。
こんな穏やかな日々が、僕らに訪れるとは思わなかった。
さらさら、さらさら、
指の間を跳ねる髪がすり抜ける。
もつれていない艶やかな髪は。
指に一度も、引っかかることもなく。
「……スレイン」
そんな夜は、無性にあの頃のことを思い出す。極秘施設でのこと。不健康で剣呑で、射抜くような瞳を僕に向けていた、世界の罪を贖う人を。
あれは四年前。まだ極秘施設にスレインがいて、面会という口実で僕が会いに行っていた頃。スレインは大人しく礼儀正しい模範的な囚人で、施設職員たちの彼に対する態度は軟化していた。
だから、油断していた。
人員の入れ替わりは定期的に少数行われる。
犯行は四人。そのうちの一人が着任したのは、スレインが収監される五年以上も前だった。同胞を導き入れ、機会を待っていたのだろう。殺すのではなく、痛めつけるのが目的の集団暴行。監視カメラはダミーに切り替えられていた。それでも発見は早かった。他の職員たちは自分の職務に忠実であり、囚人の保護に誠意を持って当たっていたのだ。発見された時、スレインは身体中は血と体液で濡れていて、青痣と傷で元の皮膚の色は判別し難い状態だった。しかし幸いにも、髪とか、指とか、耳とか、眼球とか。そういった、身体の部分はほとんど損なわれてはいなかった。そう。ほとんどは、無事だった。
左の小指と、薬指と、中指の先からじくじくと血が流れ続けていて。
爪だけが、床に落ちていたらしい。
何かの鱗のようにも見える、細長く小さな三枚の爪が。
僕はそれを、遠いところで知らされた。この隙を狙ったんだと思うと、自分に対してどうしようもない怒りが湧いた。
見た目よりも、状態は酷かった。頭を強く打たれたらしい。意識不明の昏睡状態が二週間続いた。
僕は、ICUのガラス越しにスレインを見た。何度も。身体中に傷を刻まれ、チューブを何本も腕から生やして眠る彼を見て、僕は悪い想像ばかりを巡らせてしまう。
命に別状はない、という診断。
命に。命には。
でも。
心には?
見える傷も、消えない傷も沢山ある。
この人の身体は、どうしてこんなに理不尽に、容易く傷つけられてしまうのだろう。
この人の心は、どうしてそれを受け入れてしまうのだろう。
見えない傷は、どのくらいある?
身体は治っても、その心は。
癒える日は、くるのだろうか?
目覚めた彼を、僕はどんな顔で迎えればいいのだろう。
それでも生きろ、と。
言えるのか? 僕は。
目を閉じる彼は、安らかには見えないけれど。それでも、苦悶の表情ではない。
目覚めたら、どうなるのだろう。
僕はぎゅっと目を閉じる。真っ暗な視界の中思う。思ってしまう。
……目覚めるのが、怖い。
目を開ける。モニタには、正常値のバイタルサインが表示され、ピッ、ピッ、ピッ、とガラス越しにも音が聞こえる。
拳を握る。歯を食いしばる。瞬きもせず、区切られた向こう側を焼き付けるように見る。
覚えておかなくては。きっとこれが、最後だ、と。
「待ってるから。君が、もうたくさんだって言っても。僕は待ってる」
君が目覚め、生きるのを。僕は願おうと決める。
目覚めの時は、晴れた初夏。透き通るような青い空が、揺れるカーテンの隙間に見えた。瞼が震え、ゆっくりと開いた。僕はパイプ椅子から腰を上げ、スレインの顔を覗き込む。緩慢な瞬きの後、僕と彼の焦点が合い、彼の碧の瞳が揺れた。その色を見るのは久しぶりで、僕はこんなにも眼差しが好きだったんだと思い知り、言葉を忘れて彼の瞳を見つめていた。
やがて、スレインが小さく咳き込み、声を出した。
「えっと……。……僕、何かしたんでしょうか?」
不安そうな表情と弱々しい掠れ声。その時、僕は呆然と見慣れぬ彼の表情を見つめ、そして確かに。
確かに、安堵した。
目覚めたスレインは、何も覚えていなかった。いや、それは正確ではない。日常生活に必要な知識はきちんとあって、それまでに身につけた学問やスキルは損なわれてはいなかった。幼い頃の記憶もぼんやりとだが思い出せる。彼から父の話を聞いた。それらは全て地球の思い出。
喪失は、戦争。
火星の記憶と。
月の記憶。
その狭間、その後にある、地球の記憶。
彼の、何より大切なものと。
僕が何より必要とするもの。
それが全て、消えてしまった。
ショックだった。
しかし、別の思いもあった。
これで彼は、眠れるだろう。
食べられるだろう。
笑えるだろう。
やっと、自由になれるだろう。
「伊奈帆さんは、どうして僕を気にかけてくださるんですか」
包帯だらけではあるが、様々な治療器具が身体から外れ、背筋を伸ばしてベッドに座るスレインが、僕にある時そう聞いた。
僕は林檎の皮を剥いていた。果物ナイフを持つ手が止まる。スレインはそれをちらりと見た。僕は平静を装い、くるくると林檎を回す。
「どうしてかな」
シャリシャリと、林檎の皮がリボンのように垂れ下がる。器用ですね、とスレインが褒め、僕はそうかな、と返す。
「記憶が戻れば、いいんですが」
困ったような声が聞こえた。顔を上げると、スレインは顔を開いた窓に向けている。耳のあたりにかかる髪が風で揺れた。
「それは、どうして?」
僕が問うと、スレインは顔の正面を僕に向ける。照れくさそうに目を細め、眉を下げて口を開く。
「貴方のことを、思い出したいですから」
シャリ、と皮が途切れ床に落ちた。電灯の消えた病室は白いせいで影が濃い。開け放たれた空の色を背景にして、湿った暑い風の匂いの中で微笑む彼を僕は見る。大きく浮かぶ入道雲が翼の形に見えた。
鳥ならば、このまま飛んでいけるのに。
「僕のため?」
僕が聞くと、スレインは面食らったような顔をして、その後、ふふっと小さく笑った。
「それだけでは、ないですけど」
でも、それが理由のほとんどだろう。軍関係者が何人も尋問や観察に来るが、見舞いに来るのは僕だけだ。孤独だろうし、不安だろう。
僕のことを「さん」づけで呼び、気遣うような笑顔を向けるスレインは、その根底にある無自覚な傷を知り、それを当然のことと思う。
僕は屈んで、落ちた林檎の皮を拾う。細長い赤い皮の先っぽを、指先でつまむ。指先がベタつく。屈み込んだ姿勢のままで、僕は言う。
「僕は、君が生きていてくれれば、それでいいんだ」
腰を伸ばし、顔を上げる。スレインに向き直り、彼の背中に翼がないという現実を見る。
「ありがとう。生きててくれて」
僕は覚悟を決めた。
この人を、もう二度と傷つけさせない。
守らなきゃ、と思った。世界から。スレインを。
スレインの身体上の傷が完治する頃には、逆行性健忘の状態が続くのならば、処遇を考え直す必要がある、という方針が上層部に浮上した。僕はかなり頑張って、結果的には彼を惑星間戦争の首謀者という戦犯ではなく、一般人として生かすことに成功した。
僕が彼の身元引受人となり、同居を始めた頃には、僕は二十二歳、スレインは二十四歳になっていた。
それから、もう一年が経つ。
翌朝。起きるとベッドには一人分の空白があった。照度の低さとひんやりとした水っぽさ。窓から雨の音がした。
少し緊張して、リビングに足を踏み入れる。窓際にいた。ソファに腰掛け、自分の手の表裏をぼんやり見ている。
「スレイン」
僕が声をかけると、スレインはこちらを向いた。左右非対称に眉と目を顰め、歪んだ口元で笑う。
「界塚。……おはよう」
雨の匂いと雨の音。雨の日の薄暗いリビングルームに佇むスレインに、僕は泣きたい気持ちになる。
半年くらい前だろうか。最初に"スレイン"が戻ったのは。
朝起きると、変な感じだった。妙に静かなのだ。しん、と静まり返ったマンションの部屋は自分の家じゃないみたいで、なんというか、昨夜まであった生活の匂いがきれいさっぱりしないのだ。
この日は彼と別の部屋で寝ていたから、その時はまだ気づかなかった。
朝にしては薄暗い。カーテンを開くと、雨がしきりに降っていた。感傷的な気分でほんの数秒雨を眺め、僕は落ち着かない心地で寝室を出て、とりあえず水でも飲もうとキッチンのおるリビングへ向かう。
「……え?」
ぴたりと、床に接着されたように足が止まり、動けなくなった。視点は窓際のソファ。カーテンが半分開いていて、灰色の光が窓の近くをぼんやり照らし出している。
スレインがいた。脚を組んで、ソファに深く腰掛けて。そして彼は。
不思議そうに、左手の爪を見ていた。
どうして、爪があるのだろう。どうして、痛みがないのだろう。そういう顔だった。
その時の気分は形容し難い。ぞっとした。怖かった。でもそれ以上にほっとした。
ああ、戻ってきた。
「スレイン?」
"スレイン"なんだ、とわかった。
「えっ?……界塚?」
なんだ、その格好、と彼は小さく笑ったのだ。ぎこちなく、不器用な笑顔で。
病名はない。
晴れた日も、曇りの日も、夕立も、トリガーにはならない。
雨の朝だけ。
夜更けに降り始める雨が、かつての"彼"に戻すのだ。「伊奈帆さん」ではなく、「界塚」と僕を呼ぶスレインに。
「スクランブルエッグとだし巻き卵は、どっちがよかったかな」
キッチンで出来立ての朝食を皿に盛りつつ僕が聞く。
「作る前に聞けないのか?」
そこにいるのに、とダイニングテーブルに肘をついたスレインがぼやく。
食卓が整うと、僕は両手をぱちんと合わせる。
「ほら、手を合わせて」
「……ん」
「いただきます」
「……いただき、ます」
そこには、昨晩とは違う食事の風景がある。
「ねえ、美味しい?」
「……ん」
「お茶、おかわりする?」
「いや、もういい」
ほとんど無言で、食事を終える。
「ごちそうさま」
「……ごちそうさま」
しかし、お腹も心も心地よく満たされる。
彼の幸せを思うなら、どちらがいいのかわからない。僕についても。ただ、つんけんとした「界塚」は。やはりとても懐かしい。
"スレイン"は、雨の降る日に手紙を書く。
机に向かって座る彼を、正面から少しずれた場所について眺める。本を読んだり、ぼーっとしたり。時々席を立ち、お茶やお菓子を運んだりする。雨の日にはこうして仕事を休むから、職場では変なあだ名で呼ばれているかもしれないな、と頭の端で考えつつ。
雨に包まれ、僕はスレインを見つめる。端正な額。伏目に落ちる睫毛の影。通った鼻筋。軽く結ばれた唇。
ネックレスの鎖が、雨の照度に鈍く光る。
そして、僕は思い知る。
この人はこの先、青い空を見ることはないのだ、と。
ボールペンの先を見る。ペン先にある、彼の人差し指を見る。短く切り揃えられた小指の爪が、時折戯れに噛まれるのを見る。
つるりと生え揃った三枚の爪。痕跡はもうない。それだけの時間が流れたのだ。
「スレイン」
「ん?」
声が先。次に、動かしていた手が止まる。最後に、瞳が僕を映す。
今の僕はどんな風に、彼には見えているんだろう。
「どうした?」
スレインが聞く。僕は彼の瞳から、目を逸らせずに唇を噛む。
言いたいことが、沢山あったはずなのに。透き通る碧眼を見つめていると、それらの言葉は霞のように消えてしまった。
「……いや、なんでもない」
雨音の和音。スレインがくすりと笑う。
「変なやつ」
その後は、紙を引っ掻くペンの音と、雨が天から落下する音だけがする。
やがて書き終えた手紙を、スレインは封筒に入れ、電話台の、右の引き出しに仕舞う。
彼は何も言わない。
僕も、何も聞かない。
雨は降り続いている。
「まだ、降ってるね」
「ああ」
このまま降り止まなければいい。たとえば神話の一説のように、大洪水で全てがなくなってもいいとさえ思う。
だって、僕らに世界に必要ないし、世界に僕らは必要ない。日本の郊外、古いマンションの一室。僕らにとって、ここが果ての場所だと思うから。
……なんてね。そんな子どもっぽいことを、雨の日には考える。
「コーヒー、おかわりする?」
書き仕事を終えて背伸びをするスレインに聞く。彼は肩を回しながらうーん、と唸る。
「お茶がいい」
「紅茶?」
スレインが天井を睨み口を曲げた。
「お前のやつ」
名前が思い出せなかったらしい。
「緑茶ね」
僕はケトルに勢いよく水を入れる。
その手紙を、僕は読んだことがない。
誰に書いたものかも知らない。
もし僕なら、と想像するのが怖いから。
その引き出しの取っ手は、埃が溜まりがちになる。
その後は、手紙を書き終え暇そうにしているスレインと、他愛のない話をする。僕の冗談に、スレインは笑う。その笑い方は、眉間に皺が寄っていて、口の端を僅かに持ち上げ片目を細めるという、なんとも不器用なものだが、その笑顔が見られると、僕はあの頃みたいに子どもじみた駆け引きを仕掛けたい衝動に駆られる。
口喧嘩が懐かしい。楽しかった。
でも、それはもったいない、と思ってやめる。時間は限られているからだ。
晴れ間が出来るだけ先に来るよう祈りつつ、僕は色んな提案をする。スレインは表情だけは不機嫌そうに、素直に僕に応じてくれる。久しぶりにチェスをしたり、何も喋らず本を読んだり。二人で料理をすることもある。
雨音に混ざる彼の声。雨の匂いに溶け入る彼の匂いや温度。そういうものに、時々僕は押し黙る。
雨が止まなければいいのに。
神話のように、世界の全てが流されて。
僕らも雨に溶けてしまえればいいのにな。
「伊奈帆」
僕がずっと黙っていると、スレインは決まって僕のファーストネームを呼ぶ。その声は、面会室の時と同じ低さだけれど、面会室の頃よりずっと優しい。
僕が見ると、スレインは面食らったように目を見開き、少し笑って首を振る。
「……いや、なんでもない」
僕はぷっ、と吹き出す。こんなに簡単に、嬉しくなってしまうのだ。
「変なの」
さっきのやり取りの反転だ。
幸せなのかも、しれない。
だから、終わらないでほしい。
「……あ」
スレインの顔の右半分が明るく西日を照り返す。
ああ、と思う。
雨が止んだ。
「雨が上がった」
スレインの声。
オレンジ色の日差しが広がる。スレインが瞬きをする。
長い、長い。僕にとっては、永遠にも思える瞼の開閉。
そして。
瞼が開いた瞬間に、彼の表情は切り替わる。
「あれ?僕……」
キョトンとした顔で、左右をきょろきょろ見回している。僕は彼に微笑みかける。
「椅子に座ったまま眠れるなんて器用だね」
僕が揶揄い、"スレイン"が困ったような顔で軽く睨む。
「眠気覚ましにコーヒー入れようか」
「あ、僕がします」
僕が立ち上がるより先に、スレインはキッチンにスタスタ行ってしまった。その後ろ姿を見送って、僕の視線は電話台の右の引き出しに向かう。
「あちっ……」
声に振り向く。熱すぎたポットから反射的に指を離して耳を触る、耳の近くで軽く握った小指の爪を眺めて僕は思う。
あの手紙を、いつか彼は読むだろう。いや、もしかしたら、すでに知っているかもしれない。
あの手紙には、何が書かれているのかを。
[from rain]
――どうやら、夢ではないらしい。
手紙にしては、可笑しな書き出しだ。でも、仕方がない。手紙なんて、書いたことはないし、次に書けるかわからない。
最後の記憶は、独房だ。男たちの頭の向こうに、天井の模様がぼやけて暗く黒く落ちる。痛みが遠のき、眠りのような安らかな感覚に包まれた。死ぬ時は走馬灯が見えるって言うけれど、あれは嘘だ。まあ、生きているんだけどな。
やっと終わった、と僕はその時思ったんだ。
でも、それは違った。
目覚めた時、まず雨に気づく。意識が次第にはっきりとして、そして驚く。地下の独房では、雨の音などしなかった。
ここは、どこだ?と辺りを見回す。寝心地の良いベッド。ベッドサイドのテーブルにはナイトランプ。スリッパもある。窓があり、反対側の壁面にはクローゼット。角には小さな文机がある。
清潔で整理された寝室だった。全く見知らぬ場所だった。
僕は床を踏む。また驚く。どこも痛くない。傷もないし、頭痛もない。しかも、空腹を感じた。
一体、僕はどうなってしまったんだ?
そう思いつつ、扉を開ける。次の部屋はリビングだった。大きな窓があったので、カーテンを開ける。空が見えた。曇天で、雨粒が斜線となっている。
何年振りの空だろう。
僕はなんだか少し感動して、そして焦点は窓のガラスの反射に向く。薄くだが、自分の姿が鏡のように映っていた。
見覚えのない様相に、身体中をベタベタ触る。知らない服を着て、前より歳をとっている。そして、どこにも傷がない。
手を見る。覚えてる。あの時僕は、確かに爪を剥がされたのにーー。
きちんと生え揃った爪の先は、ささくれ一つなく短く整えられている。
あれは夢だったのだろうか、それともこれが夢なのか、とぼんやり自分の手を見ていると、そう。お前が現れた。
伊奈帆。あの時のお前の顔ときたら。幽霊でも見たような、真っ青な顔だった。
でもその顔が、すぐに泣き笑いに変わった。それで、僕は思ったんだ。
この空想みたいな現実は。全部お前のおかげだろう、と。
感謝すべきなんだろうな。うん。ありがとう。
僕ら、こんな話をするような仲じゃないだろう?でも、心残りがあるといけないからな。一応ここに書いて残しておくよ。
これが最後かもしれないし。
次があった、というのは存外に嬉しいものだな。
しかし、少し驚いた。目が覚めたら、お前の隣に寝てるんだから。服も着ていないし。いつの間に、僕らはそんなことになっていたんだ?
まあいいか。別に嫌ってわけじゃない。ただ、ちょっと順番が違うんじゃないか。僕だってお前が思うほど馬鹿じゃない。気づいているんだ。僕じゃない僕がいること。まあ、お前から見れば、どちらも僕なんだろうけどな。
まあとにかく。なんか言え。ここまでしといて、同情とか憐れみってわけじゃないだろう?僕から言うのはなんか違うと思うが、どうだ?
って、言えたらいいんだけどな。お前の顔を見ていると、どうもそういう気になれない。今の話は、くだらないことに思えてしまう。
雨の降る間は、短いんだ。
できるだけ、喧嘩なんかしないで過ごしたい。でも、口を開けば憎まれ口を叩きそうになる。だからこうして、手紙を書いているってわけだ。
……お前は、これを読むのかな。
少し慣れてきた。雨の朝が、いいみたいだ。お前もそういうのがわかってきたんだろう?だって、一日中どこにも行かずに済むように、何かと準備してるんだから。
僕がこうして手紙を書いている間、お前はずっと黙っているよな。僕の邪魔にならないように、向かいに座って哲学書なんか広げて。時々、コーヒーや甘いものを差し出してくる。薄暗い部屋。雨の音を聞いて、雨の匂いの中で、お前が静かにそこにいる。時々そっと僕を見て、伏せ目がちに頬を少し綻ばせる。
そんなお前を、僕も見てるって知ってるか?
いつだって、これが最後かな、と思うけど、それらしいことは何も言えない。
僕は、お前に聞きたいことがあるんだ。
でも、それが何か、まだちょっと言葉にできない。ぼんやりとしたイメージでしかないから。
お前は、僕が元の通りだと思っているんじゃないのか?
そうじゃないんだ。
次があって良かった。
あのな。
僕は、お前に聞きたいことがあるんだ。直接聞くのが怖いから、ここに書いておく。もし読んで、その気になれば答えてほしい。
僕は、お前のことを知っている。戦争があって、敵だった。お前は僕を殺さずに、生かすために色々な手立てをとった。その延長線上に、今の僕らがあるんだろう。
そのことに、なんの疑問もない。元々、憎いだけの相手ではなかった。……こんな書き方は、今の僕らの関係からすれとなんだか誤解を招きそうだ。そういう意味じゃなくて、共感できるところがあったということだ。
同じ景色を見ているのだと思った。そして、それはお前もそうだろう?
だったら、教えてくれないか。
きっとお前も知っている。僕にとってもお前にとっても、大切だったはずなんだ。
思い出そうとすると古傷が疼くが、その理由がわからない。
僕が忘れてしまった人は、誰なんだ?




Comments